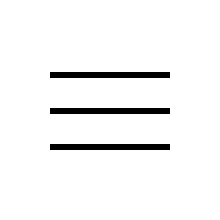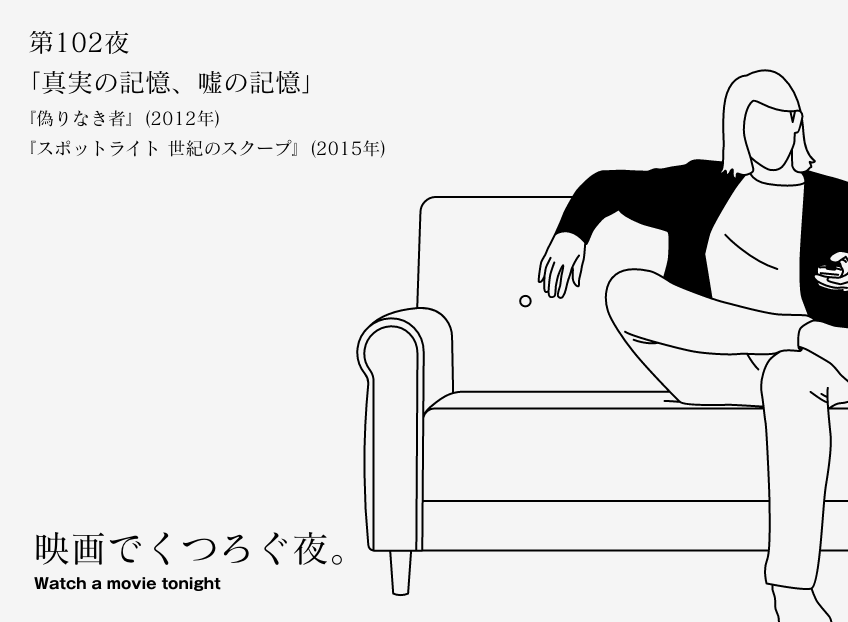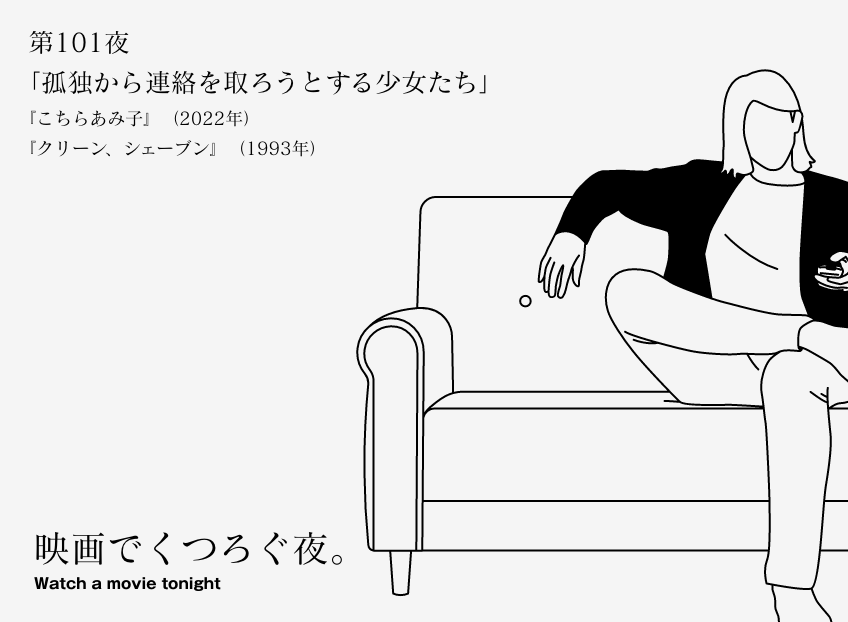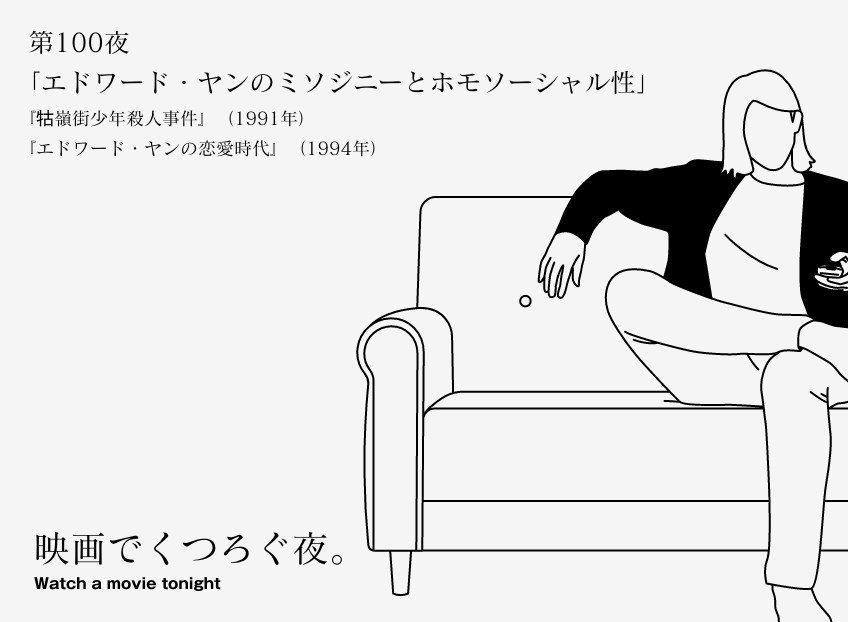真魚八重子「映画でくつろぐ夜。」 第4夜
Netflixにアマプラ、WOWOWに金ロー、YouTube。
映画を見ながら過ごす夜に憧れるけど、選択肢が多すぎて選んでいるだけで疲れちゃう。
そんなあなたにお届けする予告編だけでグッと来る映画。ぐっと来たら週末に本編を楽しむもよし、見ないままシェアするもよし。
そんな襟を正さなくても満足できる映画ライフを「キネマ旬報」や「映画秘宝」のライター真魚八重子が提案します。
■■本日の作品■■
『静かなる決闘』(1949年)
『ベニスに死す』(1971年)
※配信サービスに付随する視聴料・契約が必要となる場合があります。
コロナと映画
しばらく前から、なんとなく社会にギスギスした空気が漂っていると感じていて、そのさなかにコロナが流行し始めた。こういうとき、考えすぎる人は現象から啓示的なものを読み取ろうとしたりする。スーザン・ソンタグに『隠喩としての病い』という著書もあるが、コロナが何かを象徴しているような変な考えが頭に浮かんでしまう。現在のギスギスした人々の心境に、ネットが介在し影響を与えているのは間違いない。そしてコロナは外出を妨げ、たとえばわたしのようにオンライン飲み会もやらない人間は、本当に家族以外と会わなくなってしまった。そういう現実の付き合いが閉ざされた人は多い。生身から得る情報のシャットアウトと、それゆえによけい偏って殺伐としていく世論。コロナがその傾向に拍車を掛けている。コロナはろくなものじゃない。
もっと単純に、コロナ禍に恋人たちはどうやって出会うんだろうと、最近はたまに考える。今は大勢がマッチングアプリを利用しているらしいが、メッセージやビデオ通話でのやり取りは、当然実際に会うのが目的になる。しかし自粛が続くこの一年以上の間は、ネットを通じての関係性から、生身の対面へのハードルは上がっているんだろうなと思う。PCR検査をお互い受けて、陰性と確認したうえで会うというのは大仰なように聞こえても、実際は踏んでもおかしくない手順だ。そういうところに相手の性格をみることにもなるだろう。
対面を果たす際に、日常的な社会性があって几帳面な人なら、とりあえず相手のコロナ対処を確認すると思う。難しい話ではなくて、まず「待ち合わせの店に入ったらうがい手洗いしましょう」と一言添えるとか、どの程度の危機意識を持っているかを知ったうえでのすり合わせは、あったほうが安心だ。
でも、片方がずぼらで、一方が気を遣う人なら、出会いや婚活もぎくしゃくするだろうなと、ちょっと心配に思う。もう一生マッチングアプリなんてやる機会のなさそうな自分が考えるのも、よけいなお世話なのだが。でも自分が当事者だったらと想像すると、絶対いちいち変な気を回したりしていると思うのだ。
「コロナが治まるまで会うのは待とう」と約束していた人たちがいたのなら、どうしたのだろう。「発症してない」「他人と接触していない」期間を設けて、会うことにするのだろうか。でもそういう段取りを切り出すのは、おおごとのようで言いづらいだろうなとか、ほんとに余計なお世話だけれど、そういう愛の形が現在はあるのだろうと考えてしまう。そのほうが「うつしてしまったらいけない」という思いやりを感じるから、より信頼度が高まるかな、とか。
数年後以降に、この期間の恋愛の変化は、実際に結婚件数や出生率などの具体的な数値となって現れるのだろう。いま愛を育んでいる人々は、外出しづらい分、特定の相手と過ごす時間が増えて、二人で共に暮らす大事さや重みを感じやすいのではないだろうか。この暗い時期に結婚を視野に入れたカップルは、結束が固くうまくいくような気がする。
『静かなる決闘』
『静かなる決闘』
監督:黒澤明
脚本:黒澤明、谷口千吉
出演:三船敏郎、志村喬、三条美紀、千石規子、中北千枝子、植村謙二郎、山口勇
黒澤明監督の現代劇。戦時中、軍医として働いていた藤崎(三船敏郎)は、手術中に誤って指を切り、患者の梅毒に感染してしまう。戦後は父親の産婦人科医院で働きつつ、婚約者の美佐緒には病気の話を切り出せず、距離を置いたままで時が過ぎていく。しかし藤崎が意を決して父親に感染を告白していた会話を、見習い看護師に立ち聞きされてしまう。
梅毒は性病のイメージが強く、いかがわしい病気という先入観を持たれるため、この清廉で実直な主人公のやりきれなさは本当につらい。彼は病状での苦しみではなく、まさに病気が勝手に持つ隠喩で苦悩することになるのだ。そして生真面目であるがために、他人にうつさないよう、青年らしい欲望は抑圧して生きる決意をしている。自分を愛する婚約者を何年も遠ざけつれなくするには、並々ならぬ精神力が必要であり、その悲痛な煩悶を聞くと、どうしようもなさで心が張り裂けそうになる。このシーンの三船敏郎が狂おしく訴える演技の素晴らしさに、カメラマンが撮影中にも関わらず、胸を打たれて泣いてしまったという逸話がある。
エイズが知られるようになった時も、同性愛者とことさら結び付けられて語られ、社会にはまるで患者に咎(とが)があったかのような世論の気配が漂っていた。もちろん理由は色々あって、たとえば避妊の必要がないから男性同士ではコンドームを着用することが少ないとか、当時は出会いの場が発展場などに限られたために、同性愛者間で流行してしまったことなどがあげられる。許されない行為を自然の摂理や神秘が裁いているわけではない。コロナに関しても、不用心な会食を介して罹患することは多いけれども、感染経路が不明の人もいる。患者に対して感染対策をとっていなかったという偏見が生まれるイメージの力が恐ろしい。
『ベニスに死す』
『ベニスに死す』
監督:ルキーノ・ヴィスコンティ
脚本:ルキーノ・ヴィスコンティ、ニコラ・バラルッコ
製作:キャロリーヌ・ボンマルシャン
出演:ダーク・ボガード, ビョルン・アンドルセン, シルバーナ・マンガーノ
監督はイタリアの名匠ルキノ・ヴィスコンティ。タージオを演じたビョルン・アンドレセンの美少年ぶりは時代を超えて今も語り継がれている。ビョルンは最近、アリ・アスター監督の『ミッドサマー』で美老年ぶりも発揮していた。
作曲家のアッシェンバッハは、静養のためベニスへ赴いた。そこでポーランド貴族の少年タージオを見かけ、美しさに目を奪われる。その後も散歩中にタージオを自然と探してしまうアッシェンバッハだったが、辺りにはコレラが蔓延しつつあった。
上流社会のきらびやかだが停滞した時間が漂う映画である。主人公は優雅に毎日を過ごし、自分が蝕まれつつある老いと、もはや手に入れるものでもない少年の圧倒的な美を中心に意識が流れていく。だが彼の傍らでは消毒薬がまかれ、人々は「生野菜を食べてはだめだ」といった会話をしていることに、アッシェンバッハは気づいていないように見える。
この映画を初めて観たのは中学生くらいで、その時はアッシェンバッハがコレラの流行を知らないのかと思って観ていた。だからはやり病が恐ろしいという印象を持っていたのだが、今となってみると、もっと諦めなどの複雑な心境を込めた作品なのだとわかる。貴族趣味の退廃の奥に、空気のよどみが立ち込めた、疫病の感覚的な再現がある映画である。