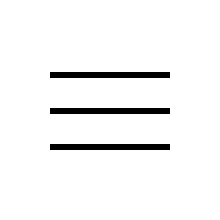燃え殻「明日をここで待っている」
一日の終わりや、疲れ切った今日を脱ぎ捨てた部屋でぽつりと明日を想うような言葉群
明日をここで待っている 第8回
「自分には何もないです」
そんな言葉で始まるハガキを昨日もらった。この時代にハガキというだけでも珍しいのに、送り主はまだ二十代の女性だった。編集者が、打ち合わせが終わったところで、鞄をゴソゴソやって、僕に渡してくれた。
丁寧な青いボールペンの文字で書かれた手紙には、目一杯の日々の不安が書かれていた。東京の郊外で一人暮らしの彼女は、派遣の仕事をしていたが体調を崩し、いまは引きこもりのような生活だという。夢はあるが、まだここでも披露できないくらいの夢だと書かれていた。そんな日々の中で、たまたま図書館で借りた僕のエッセイ本を読んで、ハガキを書きたくなったという、嬉しい内容だった。
最初に体調を崩したときは文字を追うことも難しかったらしいが、それもやっと落ち着いてきたところで、ちょうど僕の本に巡り合ったらしい。彼女が僕の本を見つけてくれた図書館は、東京だということを忘れてしまうほど緑に囲まれているところらしく、うたた寝にはもってこいなので是非一度来てみてください!と書かれていた。
僕も仕事が一番キツかったときに、図書館に逃げたことがある。僕の場合は横浜のはずれにあった神奈川県立図書館だった。そこもやはり緑に囲まれた場所で、みなとみらいの近代的なビル群がすぐそこに見えるのに、どこかのんびりとした桜木町という場所にあった。僕はまだ実家から仕事場に通っているころで、母親に仕事に行くと言って、そのまま朝から晩まで図書館にいた。図書館には食堂があって、二百円くらいでうどんやそば、団子みたいにからまったミートソーススパゲティが食べられた。僕はそこで働いていた岸部一徳に激似の店主に声をかけられる。
「学生?」ニコチン強めの両切りタバコを燻られせながら、彼は言う。僕はなんて答えたか忘れてしまったが、たぶん嘘をついた。
「まあいいや、これやってきて」そう言って、残飯をバケツに入れて僕に渡す。呆気にとられていると、火のついたタバコで食堂の裏手を指す。僕がそちらを覗くように見ると、三匹くらいの猫もこちらを覗くように見ていた。僕の職場への不登校は半年くらいはつづいた気がする。その間、僕は朝から図書館に行き、昼になると二百円でうどんかそばかスパゲティを食べて、残飯を猫に運んでいた。三匹の猫は人間に慣れきっていて、とにかく旨そうに残飯を食う。僕はその姿を見ているときだけは、現実のあれやこれやを忘れることができた。
ハガキを送ってくれた彼女に僕はハガキで返事を出した。きっとそういうものに返事を書くのは最初で最後な気がする。
彼女のハガキの最後には、「これを書いたことでだいぶ気持ちが晴れました」とあった。僕はあのときの図書館に住み着いていた猫たちの話を書いた。あの岸部一徳に激似の店主のことも書いてみた。まだ披露できない夢すら持つことができなかったあのころの自分のことを書いた。ハガキをポストに入れたとき、僕もなんだか気持ちがだいぶ晴れていた。