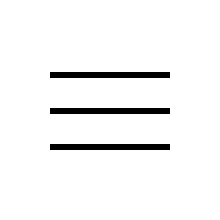燃え殻「明日をここで待っている」
一日の終わりや、疲れ切った今日を脱ぎ捨てた部屋でぽつりと明日を想うような言葉群
明日をここで待っている 第4回
「人生、四度目」みたいな人は周りにいないだろうか。僕の周りには一人、「人生、七度目」みたいな男がいる。彼は基本的に何があっても動じない。突然の地震で、僕がワタワタしているときも、静かに時計をチェックして、手帳に何かを書き込んでいた。あとで、何を書き込んでいたのかを聞いたら、明日の予定だった。彼は「食」にも執着がない。ずっと同じ弁当屋で、日替わり弁当を食べている。一度、「いつも同じで飽きないの?」と聞いたことがある。「何を食べてもそんなに変わらないよ」と素っ気ない返事が返ってきて終わりだった。何に対しても興味がないのかというと、そうでもない。彼は印刷会社の営業職なので、出力された印刷物にだけは異様にこだわる。色味のチェック、紙のチェックをしている姿を見ると、職人そのものだ。職人が過ぎて、まったく資本主義に向いていない。試し刷りやら色味チェックにこだわってしまい、限りなく利益が出ない。よって出世はしないが、クライアントには喜ばれる。人を押しのけてまでほしいものが、この世の中にないらしい。
「あいつさえいなければいいのに」と僕が思わず、そんな愚痴をこぼすと、「別にあいつがいてもいなくても、君の書くものは変わらないよ」と素っ気なく真っ当なことを返された。そうなのだ。彼の言う通りなのだ。誰が成功しても、誰が失敗しても、自分の人生の充実度には、まったく関係ないのだ。
友人が起業して成功を納め、ポルシェを買ったと聞いた。買ったポルシェの写真をスマートフォンの待ち受けにして、SNSのアイコンにして、年賀状にもしていた。そして隙あらば「ポルシェ、乗る?」と聞いてくる。最近、都内のタワーマンション最上階に住み始めたらしい。その友人のSNSは、最上階からの景色かポルシェ、予約が取れない鮨屋の写真しかほぼあがっていない。友人の幸せは、他人からの「いいね!」があって、初めて成立する幸せに見えた。そんな友人が起業する数年前、高田馬場に住んでいたとき、よくコンビニで缶チューハイをしこたま買って、ふたりして飲んだ。さきいかをべちゃべちゃ食べながら、人の悪口とエロ話をして、缶チューハイで全部飲み干したりしていた。
それは夏真っ盛りのある一夜の出来事だ。僕が仕事でどん詰まって、友人が起業についてまだ踏ん切りがつかない夜だった。風はまったく吹いていない。湿度だけがどっぷりとある、気だるい夜だった。お互い、将来の話は不安と緊張が付きまとう時期だったので、今夜はそれについては話すのをやめようということになった。コンビニで、小学生が買うような花火セットを買って公園に行った。さっきまでコーラが入っていたペットボトルに公園の水を入れて、花火の袋を開け、ライターで片っ端から火をつけて遊んだ。思えば公園で花火をするのは、数十年ぶりだった気がする。そしてそれ以来一度もやっていない。
いま、僕の家の前は小さな公園になっていて、夏休みの子ども達が、大声で笑いながら花火を楽しんでいる。僕は仕事終わりで、ソファにごろんと転がりながら、ぼんやりそれを見ている。その光景を見ながら、友人と一緒に公園で花火をやっていた真夏の夜のことを、ふと思い出していた。いま、彼の住んでいるタワーマンションからは、隅田川花火大会が上から眺められるらしい。
「一度見に来いよ」と誘われたが、断ってしまってそれっきりだ。別に昔が全部良かったわけじゃないのはわかっている。ただ、何もなかった時代、僕たちはいまよりも確実によく笑っていた気がするんだ。