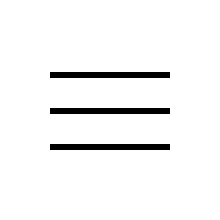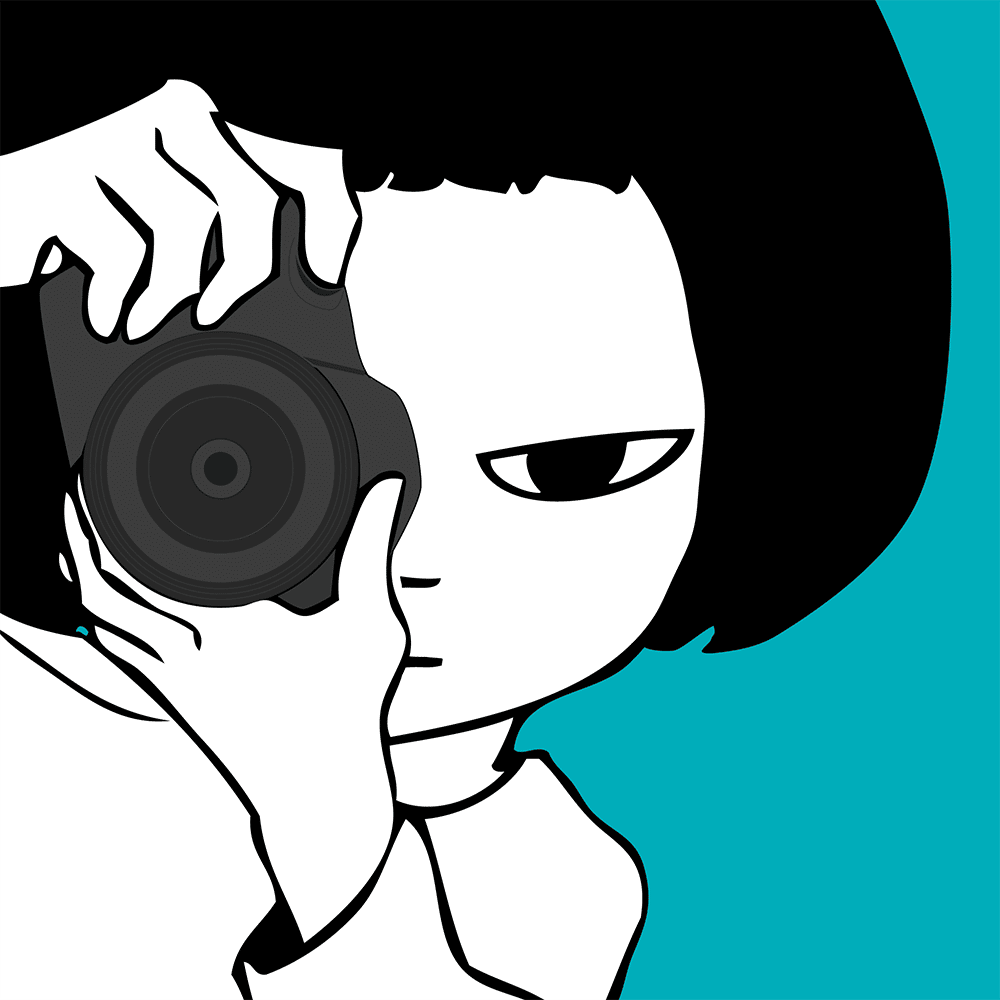「栞」
文筆家、写真家として活躍中の蒼井ブルーが書き下ろす短編小説。高校2年、地味で控えめな城戸口栞の胸の内を全6回の連載でお届けします。
⑤
「さっきさ、図書館で女の人に『彼氏?』って訊かれてたじゃん? おれのこと。あの女の人はだれ? 知りあい?」
「知りあいっていうか、播村さんっていって、行くとあいさつとかするだけです」
「そうなんだ。でも、絶対彼氏だと思われたよ。だって城戸口さん黙ってるし。ああいうときはさ、違うなら違うってはっきり言わないと。誤解されたままになっちゃうじゃん」
「……すみません」
真ん中は動揺した。一瞬見間違いかと思ったが、栞の目からはたしかに涙がこぼれ落ちている。これほどの速度で泣く人間をはじめて見た。
「いや、全然いいんだけど。別に城戸口さんのことを責めたいわけじゃないし。これはあれ、アドバイスしてるだけ。まあ、友だちでもないやつにそんなことされても、うざいだけかもだけど」
真ん中は「食べてね」とつけ加えたあと、ドリンクのストローに口をやり、うつむいて鼻をずるずるいわせる栞をしばらくのあいだ見つめた。
「よし、じゃあこれ、お持ち帰りにしよう。おれ、袋もらってくるから。帰ってから食べてよ。もう一回言うけど、おわびだから」
店を出たあと、栞は真ん中から連絡先を訊かれた。はじめての経験にどうしてよいかわからず栞が固まっていると、真ん中はこう続けた。
「城戸口さんってさ、小田切のことが好きでしょ? 違った? あいつとは幼なじみだから、おれでよかったら相談に乗るよ。まあ、これもおわびのうちってことで」
真ん中が栞の加奈子への気持ちに気がついたのは、ある意味必然といえた。
高校二年になり、新しいクラスメイトたちとの学校生活にも慣れてきた六月。真ん中は、ひとりの女子に好意を寄せられているのでは、と感じるようになっていた。
真ん中とその女子は別々のクラスだったが、真ん中のいる教室の前を通り過ぎるとき、その女子は見切れるまでずっと真ん中に視線を送り続けた。それは日に一、二度、多いときには休み時間へ入るたびに起こった。
そのことに気がついてからというもの、真ん中は徐々にその女子を意識するようになっていった。ひそかにミルコと名前もつけた。見る子、でミルコだ。
休み時間になると廊下のほうを眺め、ミルコが通るのを待ちながら過ごした。なかなかやって来ない日は自らミルコのいる教室前まで赴き、それとなく出欠を確認したりもした。
ミルコに対する感情が恋なのかは、正直なところ自分でもよくわからなかった。
七月に入るころには、教室で待っているだけでは物足りなくなり、廊下まで出て間近で視線を浴びようと試みはじめた。
しかしそこで真ん中は、奇妙な感覚に襲われるのだった。廊下で何度すれ違おうとも、目が合わないのだ。それどころかミルコは、まるで真ん中がそこに存在していないかのように振る舞った。
真ん中は少しのいら立ちとともに、ミルコへの意識をますます高めていった。
ミルコの視線の先にいるのが自分ではないと確信したのは、ある日の下校時、突然の大雨に見舞われたときのことだった。
校舎の玄関で雨宿りをするミルコを見つけた真ん中は、意を決し、はじめて彼女に話しかけた。
「おれのことって知ってる?」
ミルコは真ん中を一目見ただけで、あとはなにを言ってもうつむいたまま相手にしようとはしなかった。そしてそこに小田切加奈子がやって来て、真ん中は悟った。廊下から教室のなかへと送られるあの視線を、あのミルコの目をすぐそばで見て、悟った。
真ん中の席のひとつ前には、加奈子の席があった。
真ん中は豪雨の校庭へと飛び出し、駆けてゆくなかでもうひとつ悟った。ミルコに対する感情がなにであったかを。
──だって、図書館のときみたいにさ、一緒にいるところをだれかに見られて誤解されたら城戸口が困るでしょ。でも今日、城戸口が小田切にちゃんと気持ちを言えたら、近いうちに打ち上げでもする? そのときはおごるよ。
──したい。わたしにおごらせて。真ん中にはほんとに感謝してる。いままでたくさん励ましてくれてありがとう。
上映後、館内に明かりがともるのと同時、座席に着いたまま加奈子が伸びをした。
栞は、加奈子のデニムのショートパンツから前席のほうへと伸ばされた脚に目をやったあと、床に向かって真下へ下ろすことしかできない自分の脚を確認した。並んで歩いていてもそうだったが、座っていても加奈子のスタイルのよさが感じられて、栞はしびれた。
「なんか、思ってたのと違ったなあ。途中で寝そうだったもん。つまんない映画に誘っちゃってごめんね」
加奈子は再び座席に深く沈み込み、顔だけを栞に向けてそう言った。栞は身を起こして座席に浅くかけ、体を加奈子のほうへと向けてから首を振ってみせた。加奈子も身を起こす。そしてふたりのあいだの肘かけに両手をかけ、距離を詰めて言った。
「城戸口さん、まだ時間大丈夫? よかったらごはんでも食べて行かない? わたし、ごちそうするし」
顔が近い。昔、上映後の映画館で、こんなふうにしてキスをするカップルを見たことがある。栞は思わず目を逸らして「わかりました」と返した。加奈子は笑って「城戸口さんってかわいい」と言った。