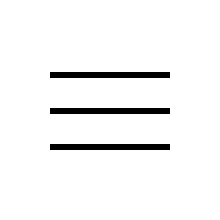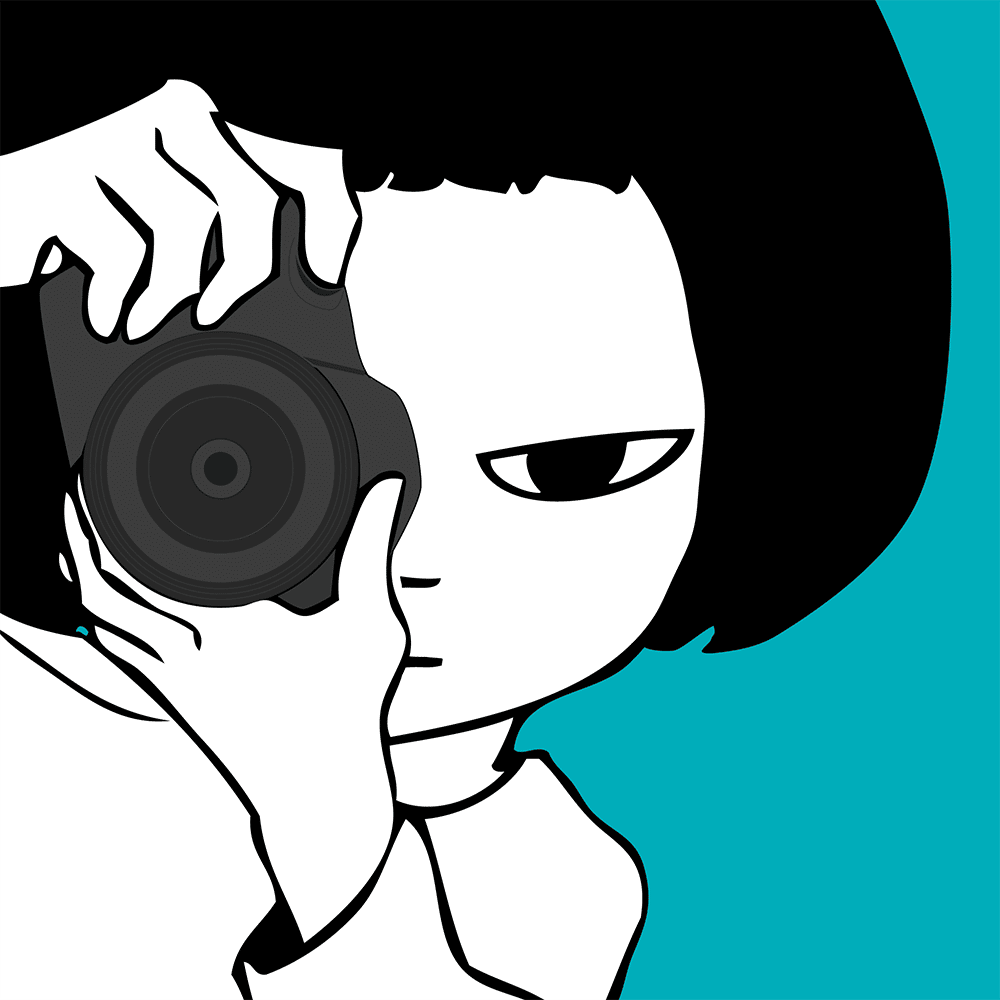「栞」
文筆家、写真家として活躍中の蒼井ブルーが書き下ろす短編小説。高校2年、地味で控えめな城戸口栞の胸の内を全6回の連載でお届けします。
④
書店のバックヤードの休憩室には栞のほかにだれもおらずしんとしていて、メッセージを受信するスマホの振動音が妙に大きく感じられた。
──えっ、小田切来たの? うそだろ、なんで? なんか話した?
──なにかの本、探してたみたい。ちょっとだけ話したよ。
──そこでバイトしてるの小田切に言ってたっけ?
──言ってない。話したのだって今日が二回目だもん。
──マジかよ。ていうか、よく話せたな。向こうから話しかけてきた感じ?
──ううん、わたしから声かけた。
──笑うわ。城戸口ってナンパできたんだ?
──できないよ。真ん中じゃないんだから。
──いやいや、おれもできないよ。それに、あいつの話しかけにくさは異常だから。それはおれがいちばんよくわかってる。
──わたしもそんなことできるわけない。仕事してたら急に小田切さんがいてね。普通に立ち読みしててびっくりした。なんでここにいるの? って思って。それでとっさに名前呼んじゃって。すごい恥ずかしかった。
──そらびっくりするわ。あいつ、夏休み中に転校なんかしやがってさ。いまは渋谷だかどこかの芸能事務所の寮に入ってるはずだからな。実家に用でもあって一瞬こっちに帰ってきてたとか?
──どうかな、そこまで話す時間もなかったし。でも、バイト終わってから映画観に行くことになったから、そのときに聞けたら聞いてみる。
──なにその神展開。そういうことは先に言えって。
──わたしもまだどきどきしてる。ここの七階と八階が映画館になってるじゃん? 小田切さん、観たい映画があるらしくて。せっかくだし一緒にどう? って誘ってくれたの。
──声に出して笑ってる。
──わたし、どうしたらいいかな?
──どうって?
──なに話したらいいかわかんないよ。
──まあ大丈夫だって。あいつは基本、女子にはやさしいから。それに、誘われたんだったら放っておいてもあいつのほうから勝手に話してくるよ。でも、おれからいろいろ聞いてたことは言うなよ? 陰でこそこそされるのはいやがると思うし。
──わかった。なんかおなか痛くなってきた。
──城戸口さ、帰り際でいいから、言えよ? 今日逃したらもう会えないかもだぞ。
──緊張する。なんて言えばいいと思う?
──この一カ月くらいのあいだ、ずっとおれに話してたことをそのまま言うだけだって。
──頭真っ白になる自信しかない。真ん中から言ってくれない? そうだ、三人で映画に行けばいいんじゃない?
──ばか、なんでだよ。じゃあもう、「小田切さんのことが好きです」だけでいいよ。どうなるにしても、あとはあいつがなんとかしてくれるから。
──うー、なんとか頑張ってみる。真ん中ってさ、ほんとに小田切さんのことよくわかってるんだね。うらやましいな。
──いやいや、前にも言ったけど、家が近くて幼なじみなだけだよ。仲がよかったのも中学に入るまでだし。最近のあいつのことだって直接聞いたわけじゃないし。母親同士がつながってて、そこから聞いただけだし。
──なんで仲悪くなっちゃったの? 小田切さんになんかきもいことした?
──うるさいな、おれのことはいいんだよ。じゃあ、頑張れよ。もし生きて帰れたら真っ先におれに連絡しろよ。はじめてできた友だちなんだよな?
──うん、する。死んじゃってもする。でも普通、友だちって一緒に出かけたりするよね? メッセージでしかやりとりしてないのに友だちって言ってもいいのかな。わたしはうれしいけど。
栞と真ん中の関係がはじまったのは七月下旬、夏休みに入って間もない日のことだった。
ランチどきで混雑しているファストフード店の狭いふたりがけの席に、栞と真ん中は向きあって座った。
「図書館なんかで会うなんてびっくりした。あそこ、よく行ってんの? 勉強しに? あ、城戸口さんも食べてよ、遠慮しないで。これ、おわびの気持ちだから。あの雨の日の。あのときはいじっちゃってごめんね」
フライドポテトを次々と口に放り込みながら真ん中が言った。栞はうつむいたまま手をつけようとしない。
「あのさ、ひとつ訊いていい? 城戸口さんってさ、おれのこと好きなの?」
「えっ」
「ははは、よかった、やっと目が合った。ほら、食べてよ。てりやきとダブチ、どっちがいい?」
「……てりやきでいいです」
「お、うまいよね、てりやき」
「……あの、話ってなんですか? 好きかってことですか?」
栞にそう言われると真ん中は紙ナプキンで手と口を拭き、背筋を伸ばすようにしてみせてから口を開いた。