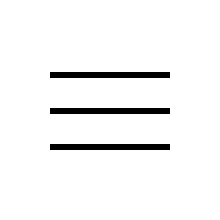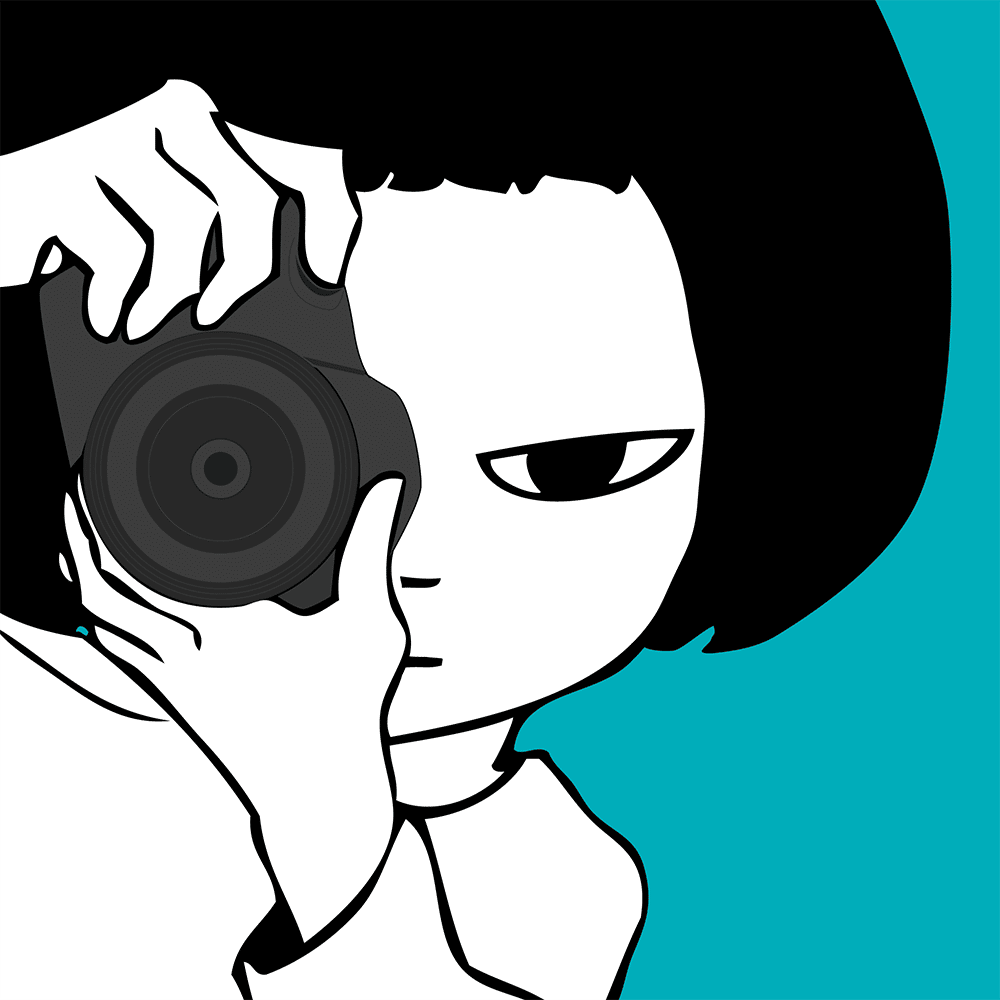「栞」
文筆家、写真家として活躍中の蒼井ブルーが書き下ろす短編小説。高校2年、地味で控えめな城戸口栞の胸の内を全6回の連載でお届けします。
③
区立の図書館は駅前の人通りが多く賑やかなところにあった。土日祝や長期休みになると、栞はほとんど毎日ここへやって来て勉強をしていた。
学習塾に通っていない栞にとって、図書館はそれに集中できる貴重な場所だった。夏や冬にはエアコンが効いていて、自分の部屋と比べれば天国のように感じられたし、ここにいれば雅美に小言を言われるようなこともなかった。
「あら、城戸口さん。おはようございます」
返却カウンターに並んでいた栞に播村貴子が声をかけた。
「おはようございます」
「今日も早いわね。わたし、あなたのこと尊敬しちゃうわ。うちの子もこうだったらいいのに」
そう言ってほほ笑む播村に、栞は首を振り照れくさそうにしてみせた。
播村は図書館の司書で、子育てが一段落したのを機に資格を生かしてここで働きはじめた。ふたりがはじめて言葉を交わしたのは四年前、栞が中学一年のときのことだった。
「どうしたの、大丈夫? なにかあった?」
閉館間際の図書館の片隅でひとり泣いている少女に、播村は声をかけずにはいられなかった。
「わたし、ここで働いてる人なの。司書っていうのよ。ここに置いてある本のことならね、全部知ってるの。すごいでしょう? ああ、でも、全部はちょっと言いすぎたかな。あなた、おうちは近く? 本は好き?」
播村にとってそれは司書としてというより、同じ年ごろの子を持つ親としてという気持ちのほうが大きかったのかもしれなかった。
「別に本が好きじゃなくても、勉強道具を持ってきてここで宿題したっていいのよ。教えてあげたりはできないけど」
白い歯をにっとみせて笑った播村の顔をよく覚えている。栞は、どこへも行けなかった自分に居場所をつくってくれた播村に感謝をしていて、それをいつかきちんと言葉にしたいと思っていた。
そしていつだったか播村がかけてくれた、「勉強はね、学生のあいだにできる貯金みたいなものなのよ」という言葉をいまでも大切にしていた。なにより彼女の柔和な人当たりが好きだった。
十三時まで図書館で勉強をしたあとは帰宅して昼食を摂り、一時間ほど昼寝をするのが栞のルーティン。そして週に四、五日は働きにも出た。
高校一年になってすぐ、図書館からほど近い大型商業施設に入るチェーンの書店で働きはじめた。栞にとってはじめてのアルバイトだった。
履歴書の志望動機欄には、「もっと本が好きになりたいです」と書いた。
「もっと本を好きになって、どうしたいですか?」
面接を担当した店長の河合征爾が履歴書から顔を上げ、指で眼鏡をすっと持ち上げて栞を見つめた。
「どうしたい……。あの、播村さんという女の人がいて、図書館の人なんですけど。本が好きかって言って。でも、わたし、本なんかちゃんと読んだことなくて。頭も悪かったし、なんにも答えられなくて。それに、お母さんともけんかしてて。あの、わたしのお母さんはいつも怒ってばかりで──」
栞の長尺で要領を得ない話に河合は、「そうですか」とだけ返した。
絶対に落ちたと思った栞だったが、翌日には採用の連絡があった。
「書店は接客の場面が限られてるし、マニュアルもちゃんとあるから。それだけ覚えておけば、まあ、なんだ、口下手でもなんとかなるから」
勤務初日、栞は河合からそう言われた。栞がすぐに辞めてしまいそうに思えた河合なりの励ましだった。
河合の心配をよそに栞の人生はじめてのアルバイトは二年目の夏を迎えていた。
栞にとって心地よかったのは、従業員同士の距離感だった。店が日ごろから盛況で多忙を極めていたため、会話は業務に関するものに限られていた。休憩時間のバックヤードもしんとしていて、他人に干渉するような空気がまったくなかった。
ここが不採用だった場合、工場の流れ作業のアルバイトに応募しようと考えていた栞は、書店というものや、ここで働く人たちがつくっている雰囲気が自分に向いていて本当によかったと思っていた。自分のような、他人とのつながりをうまく持てない人間に合う場所など、ほとんどないように感じていたから。
高校二年の夏休みの最後の週の土曜。店はいつも以上に盛況で、本を求める客たちであふれ返っていた。
先輩書店員の指示のもと、読書感想文フェアの配置換えをしていた栞がふと顔を上げると、通路を挟んですぐ向こうの棚で立ち読みをする小田切加奈子の姿があった。
「……小田切さん!」
周囲の客たちが一斉に栞を見る。気がつくと声を上げていた。雅美に対してもこれほどの大声を上げたことはなかった。
加奈子は驚いた様子で、読んでいた本で顔の目から下を隠している。そして栞に気がつくと恐る恐るそれを下ろし、胸の辺りで控えめに右手を挙げた。
白くて小さくてきれいな顔。栞は、今度は声に出さずにそう思った。