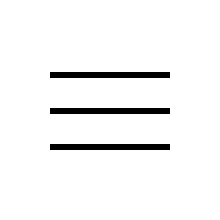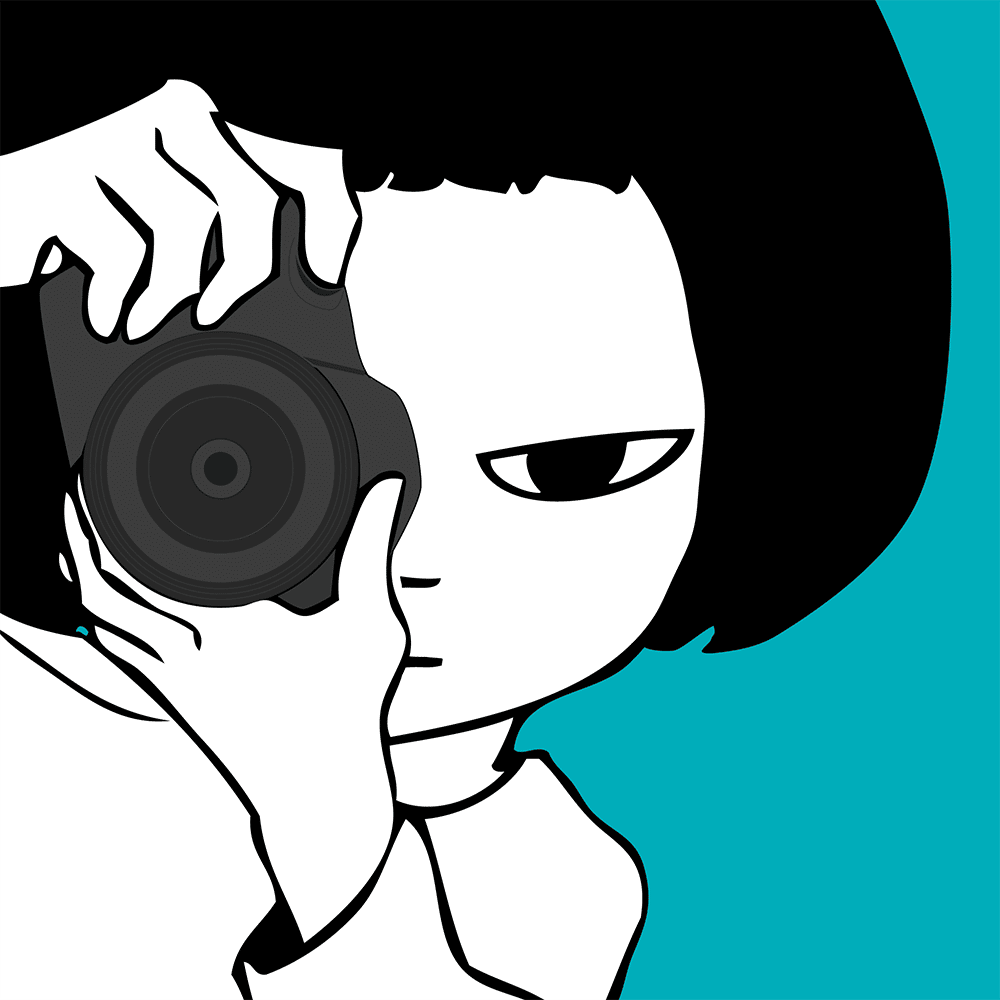「栞」
文筆家、写真家として活躍中の蒼井ブルーが書き下ろす短編小説。高校2年、地味で控えめな城戸口栞の胸の内を全6回の連載でお届けします。
⑥
映画を観て、ごはんに行く。こんなのデートじゃん、と栞は思った。こんなことになるのならもっとかわいい服を着てくればよかったとも思ったが、図書館かアルバイト先くらいしか出かけることのない栞にそのような持ち合わせはなかった。
「──でも、主演の女優さんのお芝居はよくなかった?」
パスタをフォークで巻きながら加奈子が言う。うんうん、とうなずいてみせた栞だったが、上映中も終始緊張していたためほとんど内容を覚えていなかった。
「わたしさ、あの役のオーディション受けてたんだ。結果は全然だめだったけど」
「えっ、オーディションって?」
加奈子が芸能事務所に入ったことは真ん中から聞かされていたが、彼との関係性は加奈子に内緒だったため、栞は精いっぱいの知らないふりを演じて聞き返した。
「ああ、わたしね、中学卒業したくらいのときにスカウトされて事務所に入ったんだ。で、そこからレッスンに通ったりオーディションを受けたりしてるの。家族と先生くらいしか知らないけど。あ、そっか。学校の子に言ったの、城戸口さんがはじめてだ」
「そうなんだ。わたしなんかが聞いちゃってよかった?」
「うん。城戸口さん、いい子そうだし。でも内緒ね」
「仲いい子たちにも言ってないの? なんで?」
「言ってないっていうか、まだ言えてないって感じかなあ。わたし、もともと女優さんになりたかったわけでもなかったから、本気で目指してる子たちと差があるっていうか。気持ちの時点でもう負けちゃってるんだよね。そらオーディションも受かんないよね」
栞は思わず食べる手を止めた。加奈子がいましている話が、大事な話だと思ったから。そしてますます緊張した。これまでほとんど他人とつながりを持ってこなかった栞にとって、そのような話を、人の心の奥にある思いを、打ち明けられることなどなかったから。
「で、あるとき、レッスンの先生の前でびいびい泣いちゃった日があって。先生、普段は厳しい人なんだけど、そのときはなんにも言わないで話聞いてくれて。話っていってもただの愚痴だよ? つらいですとか、わたし向いてないですとか。だめすぎて笑っちゃうよね」
にっこりほほ笑んだ加奈子はずっと年下のように幼く見えて、栞は、いつもきれいでかっこいい彼女のことをはじめてかわいいと思った。
「でも、それがきっかけでちょっとは変われたかなって思う。口にできなくて、ため込んでばっかだったものをばーって吐き出して、すっきりしたっていうか。そしたらだんだん自覚も出てきて、もっと頑張りたいって思えて。そう、今年の夏から事務所の寮にも入ってね、学校も芸能コースのあるところに転校したんだ」
栞は、加奈子が人知れず苦しんでいたことに驚いた。そしてそのあと、安堵した。完璧な人間のように思えていた加奈子が、これまでの自分と同じように、気持ちをうまく言葉にすることができないでいただなんて。
加奈子に言われるまで、栞は自分が泣いていることに気がつかなかった。
「あーん、なんで? わたし、なんかいやなこと言っちゃった?」
テーブルを挟んで向きあっていた加奈子が、慌てた様子で栞の隣にやって来て腰を下ろす。ふわっといい匂いがしたあと、栞は加奈子の腕と胸に包み込まれた。加奈子の体は大きくて、あたたかかった。このまま泣き続ければ、ずっとこうしていられるだろうか。
小田切さんのことが好きです。いつも遠くから見ていました。あなたがわたしを知る前から、あなたのことが好きでした。
「どうやったらそんなにぽろぽろ泣けるの? 今度レッスンしてくれない?」
加奈子の言葉に栞は泣きながら笑った。「いいよ」と栞が返すと加奈子も笑った。
「本当に素晴らしいです。ご家庭ではどのような教育をされていますか? ぜひお聞きしたいです」
高校三年の七月。進路を見据えた三者面談の場で担任は、栞の学力の伸びを絶賛した。
「わたしはなにも」と雅美はぶっきらぼうに返したが、担任から挙げられたいくつかの有名大学と、「栞さんにとっては夢ではありません」という言葉を聞くうち、「そうですか、この子が」と表情を緩めた。
「勉強に必要なものがあったらなんでも言いなさい」
面談後、雅美にそう言われた栞は「部屋にエアコンをつけてほしい」と返したが、まさかその足で家電量販店へ連れていかれるとは思いもしなかった。
「好きなのを選びなさい」
子どもにお菓子でも選ばせるような口ぶりで雅美が言う。
栞は急な展開に理解が追いつかず、ずらりと並ぶぴかぴかのエアコンを前にしばらくのあいだ呆然と立ち尽くした。そして数日後には業者がやって来て、栞の四畳半の部屋に段取りよく「勉強に必要なもの」を設置していった。
この日を境に栞は図書館通いをやめ、雅美のサポートのもと、わずかな時間も惜しんで受験勉強に取り組んでいった。
書店のアルバイトも同時期にやめた。
「長いあいだお疲れさまでした。城戸口さんみたいないい書店員さんがいなくなっちゃうのは残念だなあ。受験が終わったらまた考えてみてくれない? うちはいつでも歓迎だから」
最終日の退勤後、店長の河合はそう言って栞を労った。
「今日までお世話になりました。最初は不安だったんですけど、このお店だから続けられたんだと思います。はじめてのアルバイトがここでよかったです。本当にありがとうございました」
人生ではじめて、ちゃんとした別れのあいさつをした。そのわりにすらすらと言えたので、なんだか大人みたいだ、とわれながら思った。
従業員用のエレベーターまで見送ってくれた河合が、扉が閉まるとき深々と頭を下げたのを見て、栞は一瞬で涙があふれた。
家までの帰り道。自転車で七月の夜風を浴びながら、いつもより少し遠回りしてみる。
小さいころから、自分の言ったことやしたことでだれかを傷つけたり、きらわれたりするのがいやだった。そうして思いを言葉にすることをためらうようになり、どんどん他人とつながりを持たないように、持てないようになっていった。
いまもあのころのままでいたら、頭を下げて見送る河合の姿に涙もなにもあふれなかっただろう。
加奈子の腕のなかで笑ったりできなかっただろう。
真ん中の励ましに勇気をもらったりできなかっただろう。
播村さんご無沙汰しています。よく自習室を利用していた城戸口栞です。本当は直接お礼が言いたかったのですが、緊張してうまく話せなかったら困るので手紙を書きました。字が汚くてすみません。
先日、第一志望の大学に合格することができました。合格の二文字を見たとき、いちばん最初に播村さんのことが思い浮かびました。覚えてらっしゃるかわかりませんが、昔、播村さんは泣いていたわたしを心配してくださり、図書館に通うきっかけをつくってくださいました。
わたしは昔から人と関係を築くこと、コミュニケーションを取ることが苦手で、学校でも家庭でもまったくうまくいっていませんでした。そのなかでどんどん無気力で投げやりな考えになっていきました。あのとき播村さんが声をかけてくださらなければ、いまでもわたしはなにに打ち込むわけでもなく、人生をぼんやりと送っていたと思います。
うちは母子家庭で塾へ通う余裕がなく、ここで勉強できたことはとてもありがたいことでした。成績が少しずつ上がっていくにつれて、学力以外の面でもだんだん自信が持てるようになっていきました。アルバイトをはじめられたり、友だちができたり、好きな人ができたりもしました。わたしにとってそれは奇跡の連続のようなことでした。
人はひとつのことがよくなれば、そのほかのこともよくなっていけるのだと知りました。だからまず最初のひとつに一生懸命になればよかったのですね。ここへ通った日々のように。
春からは実家を離れてひとり暮らしをはじめますが、帰省するときは必ず利用しに行きます。播村さんはわたしの恩人です。大切なことを教えてくださりありがとうございました。どうかお元気で。
城戸口栞