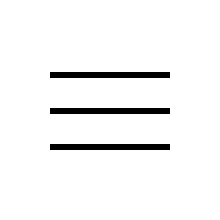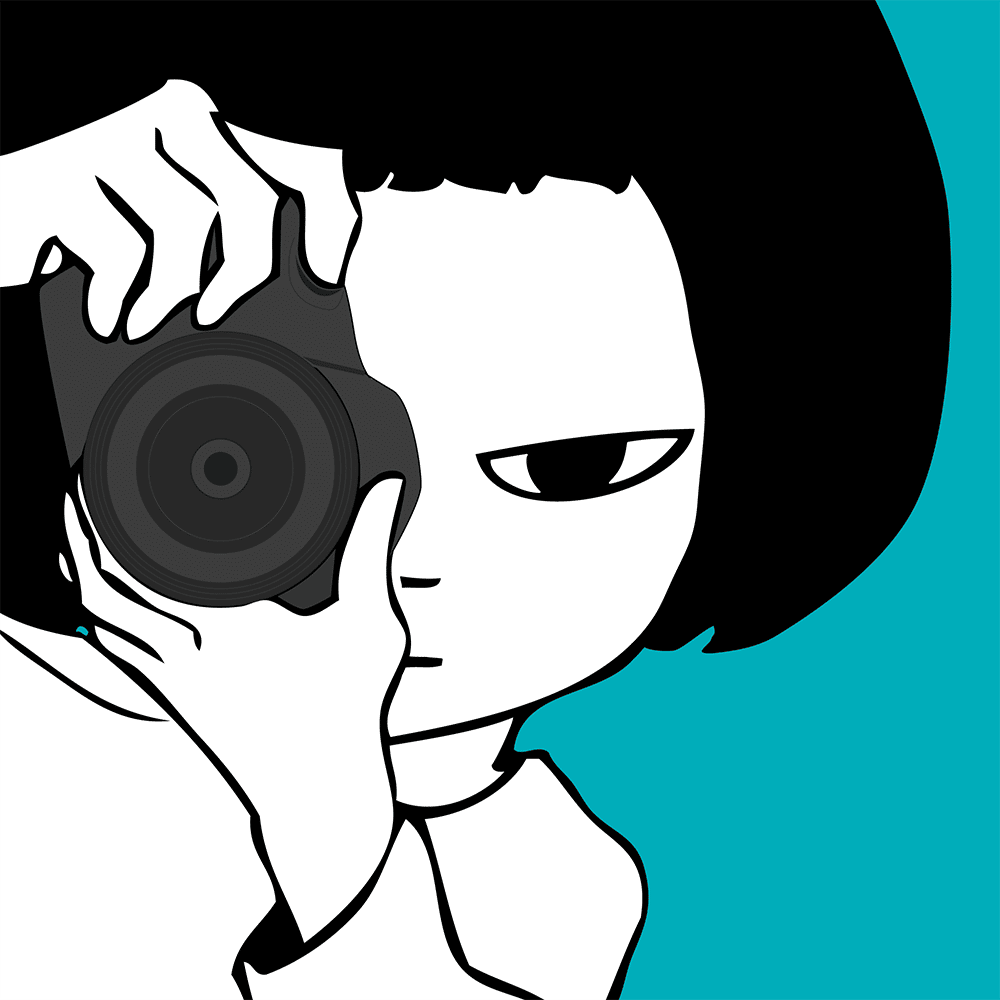「栞」
文筆家、写真家として活躍中の蒼井ブルーが書き下ろす短編小説。高校2年、地味で控えめな城戸口栞の胸の内を全6回の連載でお届けします。
②
栞の高校二年の夏休みは、昨年と同じルーティンで流れていった。
栞は部活動をしていなかったので休みのあいだ学校へ行くことはなかった。中学ではいずれかの部に所属しなければならない決まりだったため、女の子ばかりで少しは緊張しなさそう、部員数が多いから注目を浴びなさそう、といった理由から吹奏楽部に入ってはみたが、先輩との上下関係があまりに厳しく、恐ろしくなって一学期の途中には行かなく(行けなく)なった。
また他人とほとんどつながりを持っていなかったので、誘われて出かけるようなこともないし、ましてや旅行の計画などもなかった。しかし暇を持て余しているというわけでもなかった。むしろ栞自身は、忙しい、時間がない、とすら感じているのだった。
夏場の栞の朝は風呂に入ることからはじまった。昨晩も入っているのに朝にももう一度入った。これは栞が神経質なほどにきれい好きであるから、というわけではまったくなく、もう、仕方なく入っている、という表現が正しかった。
というのも、栞の四畳半の部屋にはエアコンがなかった。リサイクルショップで買った扇風機が一台あるものの、七月下旬のそれは単に生ぬるい室温を循環させているだけで、涼風の“りょ”の字もなかった。
暑さと寝汗で気持ちが悪くなり、六時にはたいてい目が覚めた。シャワーを浴びながら、なんでエアコンがないの、そのうち熱中症になって死ぬかも、こんな家早く出たい、といつものように思う。頻繁に悪夢を見るのも寝苦しさのせいだと栞は確信していた。
「お母さん、もう仕事行くから。お昼は冷蔵庫に入れてあるから」
風呂場からリビングに出てきた栞に、シンクで洗い物をしながら城戸口雅美が言った。
「うん、ありがとう」
栞は冷蔵庫を開け、そうめんだったり、納豆だったり、オクラだったりを確認してから、麦茶をグラスに注いで一気に飲み干した。
濡れ髪のまま部屋に戻り、扇風機の前に座り込んで強のスイッチを入れた。目を閉じると、窓の外から聞こえるセミの鳴き声が一段と大きくなったように感じられてうんざりした。
お母さん、早く仕事に行かないかな。朝、風呂あがりの栞が髪を乾かすのは、雅美が出勤したあとと決まっていた。リビングにある城戸口家一台きりのエアコンをフル稼働させてだ。
雅美は、栞がエアコンを使うことを露骨にいやがった。それは雅美が痩せ型で極度の寒がりということもあったが、無駄な出費をきらっていることによるものが大きかった。
中学一年の夏、「どうしてもエアコンを使いたいなら、あんたが働いて電気代を払いなさい」と雅美に怒鳴られた栞は、人生ではじめての家出をした。
しかし頼れる人間もおらず、現金の持ち合わせもない栞に行く当てなどなく、過去に一度だけ利用したことがあった区立の図書館で閉館時刻までしくしく泣いて過ごした。わずか二時間半の、しかし栞にとっては悔しくて忘れることのできない家出だった。
城戸口家は栞とその母、雅美とのふたり暮らしで、栞が小学二年に上がるタイミングで現在の家へ引っ越してきた。
引っ越し前、雅美から、次の家はマンションの最上階の角部屋だと聞かされていた栞はわくわくして、転校する心細さも幾分紛れたりしていたのだが、実際にやって来ると想像していたものとは随分違った。
東京の外れのその築年の古い公営団地は、都心の管理が行き届いた高層マンションで育った栞には気味が悪く映った。
最上階とはいっても五階建ての五階で、ベランダや窓からの眺めは同じ造りをしたすぐ隣の団地で占められていた。またエレベーターがなく、もし忘れ物でもしようものなら地獄の階段ダッシュをしなければならなかった。
前のおうちに戻りたい。暮らしはじめて間もなく、栞はそう雅美に訴えたが、「恨むならお父さんを恨みなさい」と相手にしてもらえなかった。
小学二年の栞には、その言葉の意味がよくわからなかった。しかしときが経つにつれ、両親が離婚したのは父の浩太郎が事業に失敗し、多額の負債を抱えたのが原因だということ、そして雅美こそが浩太郎を恨んでいるのだということをなんとなくも理解していった。
雅美の出勤を見届けたあと、栞はリビングにやって来てエアコンの電源を入れた。
温度は十八度に、風量は強に変更する。部屋からは小さな三面鏡を、風呂場からはドライヤーを持ち出して食卓の椅子に座る。リビングの一角に、栞の小さな美容室ができ上がった。
髪を乾かし終えたあとは温度を二十八度に、風量を弱に戻してから電源を切る。床に落ちた髪はコロコロで一本残らず絡め取る。栞はてきぱきと証拠隠滅を図ってから、トーストとゆでたまごの朝食を手早く済ませ、外出の準備に取りかかった。
目的地の図書館までは、自転車で二十分ほどだった。
ノートやテキストや借りた本などでリュックがずしりと重かったが、スピードに乗るとそれほど気にならなかった。団地群を抜けると真っ青な空が高く広がった。遠くの濃い白の雲がまるで波のように見える。栞は深く息を吸って、ペダルに一層力を込めた。