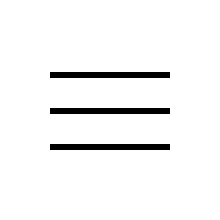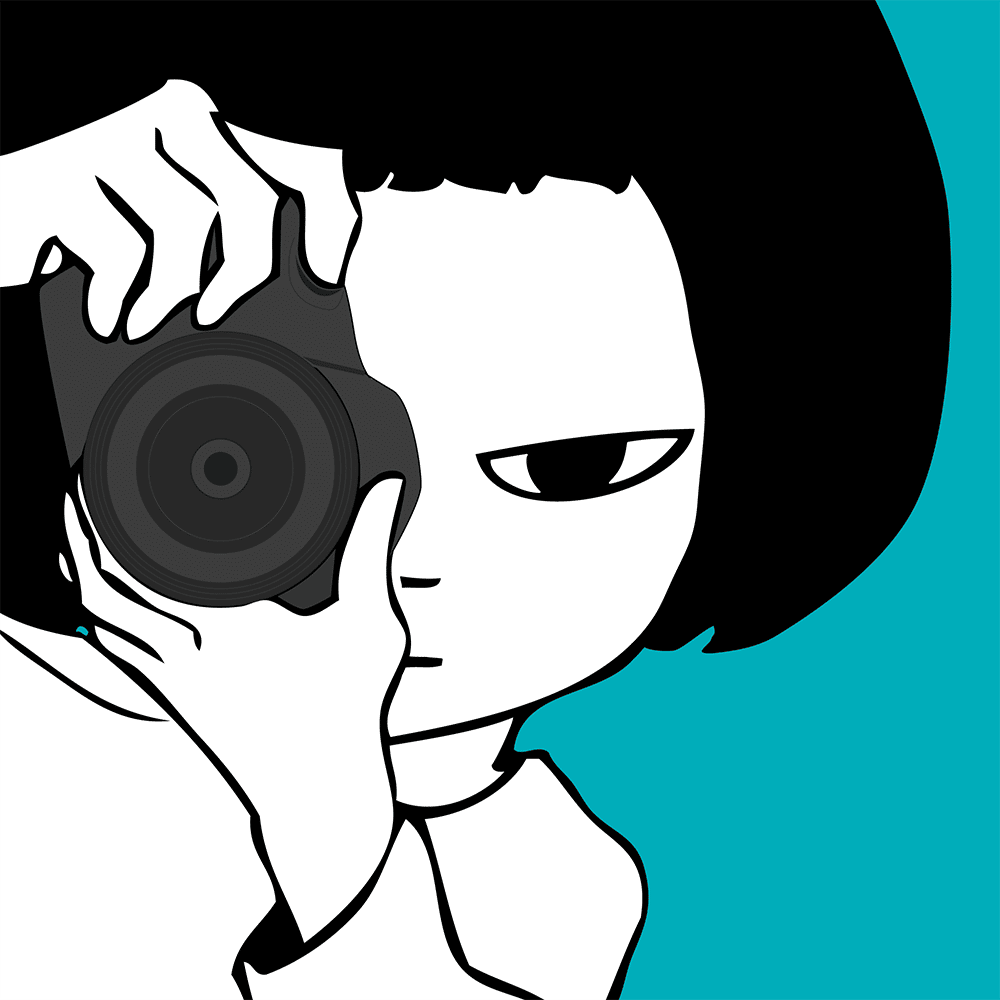「栞」
文筆家、写真家として活躍中の蒼井ブルーが書き下ろす短編小説。高校2年、地味で控えめな城戸口栞の胸の内を全6回の連載でお届けします。
①
地味で控えめな城戸口栞にはじめて友人と呼べるものができたのは、高校二年の七月のことだった。
下校時、校門を出た辺りで突然の豪雨に見舞われた栞は、校舎の玄関まで駆け戻って小降りになるのを待つことにした。玄関は栞と同様に傘を持たない生徒たちで見る見るあふれ返った。
「城戸口さん、おれのことって知ってる?」
振り向くと名前も知らない別のクラスの男子が三人並んで立っていた。薄ら笑いを浮かべて栞をじろじろと見ている。
「じつはおれさ、透視できるんだよね」
真ん中が髪に手をやりながら得意げな顔で言った。
「──今日、ブラ白でしょ? 当たった?」
栞のひどく濡れたシャツが肌に張りついて、下着が透けて見えている。
「ははは、やめとけって。でもまあ、ブラは白がいちばんだけど。なあ?」
真ん中からバトンを受け取ったかのように左がそう言って、すぐさま右につないでゆく。
「だよな。城戸口さん、おとなしそうに見えてよくわかってるわ。彼氏とかいるの?」
受け取った右もきっちりと自分の仕事をする。
「城戸口さん、意外とおっぱい大きいもんね。もしかして、やりまくってたり? おれとかは、どう? だめ?」
再びバトンを手にした真ん中がぐいっと一歩前に出て、身長一五一センチの栞に目線を合わせるようにして言った。
気の弱い栞には、うつむいてやり過ごすことしかできなかった。周りには栞と同じクラスの生徒たちもいたが、止めに入るでもなく一定の距離を取って、それぞれの会話を続けたり空模様を眺めたりしていた。
栞は鼻の奥がつんとして、じわじわと涙が込み上げてくるのがわかった。やだな、なんで泣くの。こんな人前で泣きたくない。傷つくと言葉よりも先に涙が出てしまう自分を栞は恥じ、心底きらっていた。
「うわ、めちゃめちゃ降ってんじゃん。聞いてないし。ちゃんと仕事しろよ、気象予報士」
ひとりごとというよりは、まるで周りに聞かせるような口ぶりで小田切加奈子が言った。そして三人リレーの前までやって来て、彼らの顔をひとりずつゆっくりと覗き込み、今度は声を潜めて言った。
「透視、できるんだよな? じゃあ、わたしのブラも何色か当ててみろよ。外れたら全員殺すからな」
「……小田切、おまえさ、うぜえよ」
一瞬たじろいだ真ん中だったが、そう言うと左右を引き連れて豪雨の校庭へ飛び出し、そのまま校門の外へと駆けて消えていった。
高校二年になっても他人とほとんどつながりを持たず、同じクラスの生徒であっても全員の顔と名前が一致するか自信のない栞だったが、加奈子のことは知っていた。
同性の栞から見ても加奈子は息をのむほどにきれいだった。身長は一七〇センチくらいもあって手足がすらりと長い。しかし肩幅が狭く顔も小さいので、同じくらいの身長の男子たちと比べると威圧感はなかった。
加奈子と校内ではじめてすれ違ったとき、彼女の周りにだけ照明が当たっているように見えた。栞は妙にどきどきして、ファッションモデルを間近で見るとこんな感じなのだろう、と思った。
「城戸口さんだっけ? 大丈夫だった?」
切れ長の目のなかの黒々とした瞳が栞をじいっと見つめる。栞は加奈子と体がまっすぐになるよう向き直してから、目を合わせたまま少し大げさにうなずいた。
艶やかな髪が胸の下辺りまであって、毛先が二、三段緩やかに巻かれている。わたしもこんな髪がいい。絶対に似合わないと思うけれど。栞は美容室で勧められ断りきれずにやってみたボブが失敗だったと思っていて、学校では後ろでひとつに結っていた。
「ね、わたしのリュック持っときなよ」
栞は加奈子から手渡された黒のアウトドアの大きなリュックを言われるまま手にしてみたが、「そうじゃなくてさ」と加奈子は笑みを浮かべた。そして栞の濡れたシャツから透けて見える下着を隠すようにリュックを体の前で抱えさせ、左右のショルダーハーネスをそれぞれ栞の肩にかけた。
「これでよし。乾くまで、ね」
前には加奈子のリュックを抱え込み、後ろには自分のリュックを背負う栞の姿を「小学生の罰ゲームみたい」と加奈子は言ったが、栞は「ありがとう」と言った。