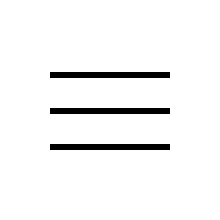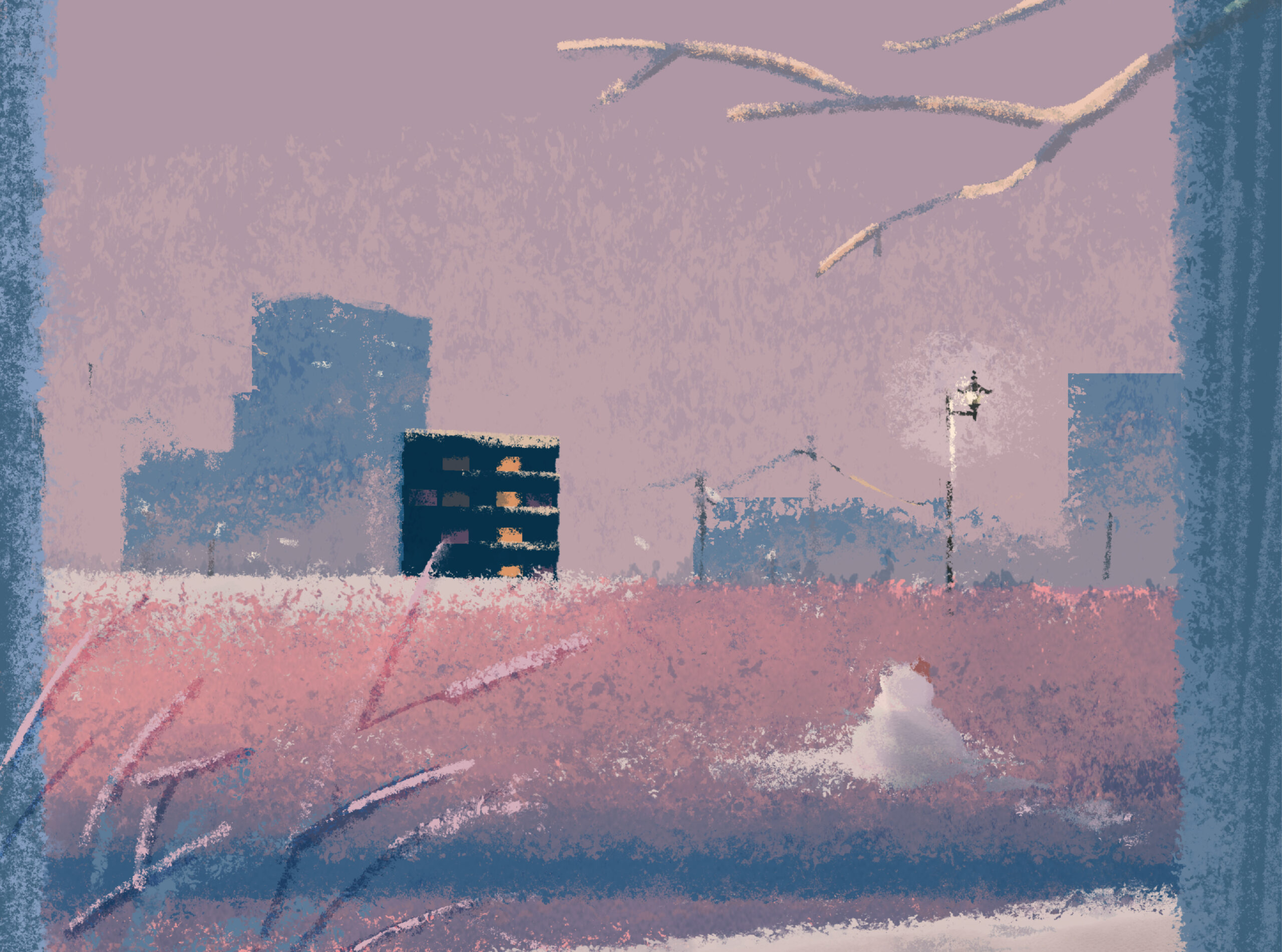「雨の夜にだけ会いましょう」
「定期的に集まろうぜ」と言い出した飲み会は二回目が開催されない。
仕事も遊びの約束も、数週間先の予定を詰められるとなんだか心が重くなる。
「もっと雑で、ちょうどいいこと」を求めて、無責任な願望を言葉にしてみるカツセマサヒコの妄想コラム連載です。
第七夜 秋に折れたヒールとレイジーウォーキング
誰にも会わない休日に限って服装や髪型がとてもうまくいったり、誰にも会いたくないと思うのに一人でいるのは寂しいと思ったり、重い腰をあげてみたものの大体のイベントや映画の上映/開演時刻にギリギリ間に合わない時間だったり。
そういう、自分と世界がうまく噛み合ってくれないような、やるせない一日があったとします。でももう私服には着替えちゃったし。なんなら結構オシャレしちゃったし。ここまで来たら出かけないと損でしょ、と、玄関を飛び出しました。
街は、秋です。ふと住宅街の角を曲がると、キンモクセイがオレンジ色の小ぶりな花を咲かせていました。
「お前、キンモクセイだったんか!」
去年も一昨年もその前も、同じリアクションをした気がします。冬から夏にかけて、まったく知名度のないモブ木(もぶき:詳しくない人から見たら全部同じような木と捉えてしまうくらい特徴のない木)みたいなツラしておいて、いきなり秋になった途端にバーンと存在感を出してくる。美術の時間のときだけやたら目立つやつがクラスにいたな。とか思いながら、さらに足を進め、電車に飛び乗ります。向かう先は、どっかのオシャレな街。
オシャレな街は、歩いている人たちがみんなモデルです。モデルみたいじゃなくて、モデル。全員事務所所属。宇宙人みたいに小さな頭と、宇宙人みたいに長い足。宇宙人みたいに細い腕で、宇宙人みたいに小さなバッグを持ち歩いています。まるで僕らはエイリアンズ。そんな世界に迷い込んだ私は、とびきりオシャレしたはずの自分の格好が、あまりにも芋すぎて驚き、悲しみ、途方に暮れます。
結局は、顔とスタイルの問題なんだよな。
この期に及んでルッキズムに囚われてしまう悲しい人間。ため息がもれつつも、でもやっぱりオシャレな街っていいなと、スタバでフラペをチーノしながら、予定のない一日をだらだらと過ごしています。
本屋に寄ったり、絶対に手が届かない値段ばかりの服屋にそれっぽい顔をして入ってみたり、ベランダで洗濯物を干すときに使うサンダルがなかったなとスリーコインズで買ったりして、たまにはこんな日も悪くないと思っていたそのときです。オシャレな街を颯爽と歩いていたモデルな女性が、突然、バランスを崩して転びかけました。
おお、何事!? と思って足元を見てみれば、なんとまあ、細くて高いピンヒールが、ボキィッと根っこから折れてしまっているじゃないですか。
明らかに困った様子のモデル。その前をいよいよ通りすぎるかどうかの私。しかし、この状況における正解は、すでにわかっていたのです。
「あの、よかったら、サンダル使います?」
この資本主義の巣窟みたいな街において、紙袋から取り出された、激安サンダル。しかし、モデルな女性は嫌な顔をするどころか、心底助かった様子で、目を細めてくれるのです(なぜなら妄想だから)。モデルな女性は、まだ値札のタグが付いているサンダルを見ながら言いました。
「ありがとうございます。でも、どうしてサンダルなんか」
「いえ、こんなこともあろうかと思って(キリッ)」
「そうだったんですね! 助かります、ありがとうございます!」
んなことあるわけねーだろうが。お姉さんはすぐにヒールをサンダルに履き替えると、宇宙人のようだった身長が急に小さくなり、僕の横に並んで歩き出しました。
「ちょうどヒールに疲れてたので、よかったです。ありがとうございます」
「いえ、なんかすみません、そんな安いもので」
「いえいえ。なんか今日、あんまり運が良くない日だったから、一つでも救われてうれしいです」
「わ、そうだったんですか?」
秒で好きになってしまった僕はモデルなお姉さんの横顔を見つめながら、一緒に靴の修理屋さんを目指します。お姉さんはオシャレな街を寂しそうに見回しながら言いました。
「なんか、誰にも会わない休日に限って服装や髪型がとてもうまくいったり、誰にも会いたくないと思うのに一人でいるのは寂しいと思ったり、重い腰をあげてみたものの大体のイベントや映画の上映/開演時刻にギリギリ間に合わない時間だったり。今日は、そういう日だったんです」
お、俺もー!!!!!! それ、俺もーーーーーー!!!!!!!!
大興奮状態になった僕は何度も何度も頷きながら、これはもしかしたらものすごくハッピーでラッキーな出逢いを果たしてしまったかもしれない、と思っていました。しかもこちとら、サンダルを貸した身なのです。貸したということは、返す日もあるということ。もう一度このモデルなお姉さんと会えるのはほぼ確定なのだッ!と希望に満ち溢れたその瞬間でした。
「あ、サンダル、買い取ってもいいですか。なんだか一度履いたものを返すのが申し訳ないので」
「いやいやいや! 全然! むしろあの、一度履いてもらったものを使いたいので!」
一瞬ドン引きした表情を見せるモデルなお姉さん。完全に人の道を踏み外してしまった私。エイリアンはこちらでした。そこからは絶妙な距離を保たれつつ、500円という少しだけ割高なかたちで小銭を渡され、僕のサンダルは無事に手元を離れていくことになりました。
このくらい。このくらい雑で、ちょうどいい出来事が、来世あたりで起こりますように。
第八夜へ続く