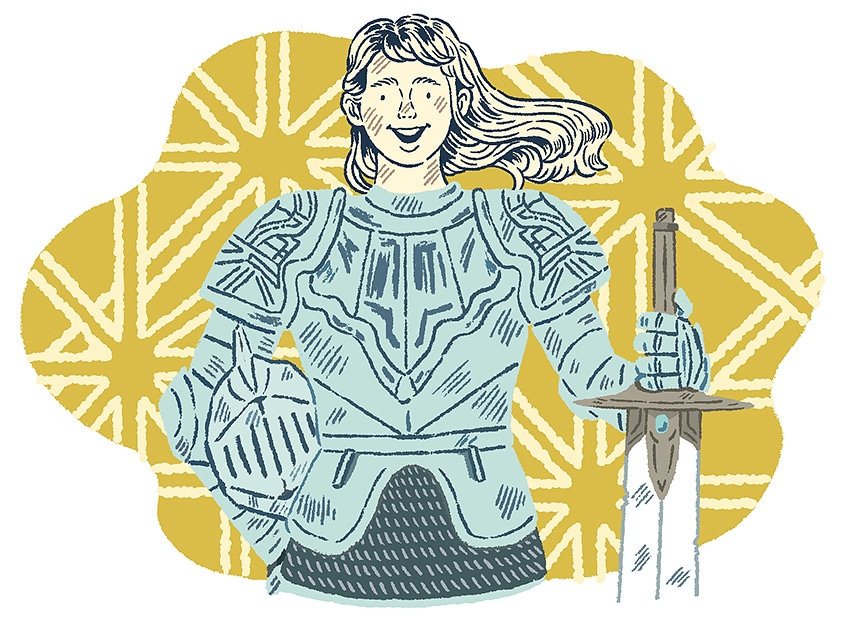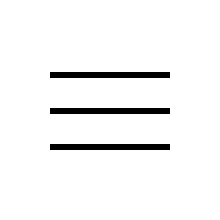「おつかれ、今日の私。」vol.8
東京生まれの日本人。
現在、TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」のMCを務める人気コラムニストで作詞家、プロデューサーのジェーン・スーが、毎日を過ごす女性たちに向けて書き下ろすエッセイです。
おつかれ、今日の私。 vol.8
「みんなでウワーッてなれればいいの。イエーイ!って。それだけだよ、大事なことは!」
散々怒って散々泣いたあと、べろんべろんのケイミ先輩の口からいつもの台詞が出たのを合図に、会はお開きになった。壁の時計をチラ見すると、すでに午前1時を回っている。明日も仕事だっていうのに、うちの会社の人たちは、なんでこうも痛飲したがるのか。
下戸の私は毎度の長丁場に辟易としながらも、バリバリ働く先輩たちから飲みに誘われるのはやはり嬉しく、いつだってホイホイついていった。うちの会社は、女の先輩たちがすべからくカッコイイのだ。みんなめちゃくちゃ仕事ができるし、お酒の席の失敗や取引先との喧嘩など、アウトローチックでド派手なエピソードにことかかない。ケイミ先輩たちは気が強くて、誰が相手でも絶対に退かないので惚れ惚れする。こんな人たち、いままで生きてきて、どこでも会ったことない。
ケイミ先輩は上司たちからも一目置かれていて、新しいプロジェクトが始まるときは、たいてい最初に声を掛けられていた。ケイミ先輩が担当すると決まると、これは大事な案件なんだと、他の社員が襟を正すくらいの重要人物。社外のお偉方からも可愛がられていて、ぞんざいな口を利いても、ケイミ先輩はニコニコ許されていた。
新入社員の頃、女子校育ちでのほほんとした私は、体育会系っぽいケイミ先輩たちの流儀に馴染めなかった。若者特有の根拠ない自信もあったし、自分から慕っていく術すら知らなかった。むしろ、向こうから仲良くしてくれるものだとばかり思っていたのに、先輩と名の付く人たちはみな愛想が悪いので最初は面喰ってしまった。
なりふり構わず働いていると、ようやく認めてもらえたのか、ケイミ先輩は頻繁に私を誘ってくれるようになった。よく飲むなぁ~なんて思いながら、ケイミ先輩からの誘いを待って、仕事終わりに社内をウロウロしていたことが何度もある。なんやかんや言って、破天荒なケイミ先輩の話を聞くのが大好きだったから。
酔いが回ってくると、ケイミ先輩はいつも怒髪天を衝く勢いで怒りだす。筋が通らないことが大嫌いだからなのだけど、よくもまあ毎度毎度、仕事でそこまで真剣に怒れるよなと、私は不思議な気持ちで眺めていた。怒りまくったあとは必ず泣きだすのだが、ケイミ先輩の涙はいつも悔し涙だった。あの頃を振り返ると、私はただただ若すぎて、ケイミ先輩がなにに怒り、なにを悔しがっていたのかちっともわかっていなかったと思う。
ある日、耳を疑うようなニュースが飛び込んできた。ケイミ先輩が、結婚を機に退職するという。遠距離恋愛中の彼がいるのは知っていたけれど、まさか結婚退社するなんて。そういう決断から、いちばん遠い人だと思っていた。あんなに仕事が好きだったのに。土日も祝日も、仕事しかしてこなかったのに。「女って、こうやって仕事を辞めちゃってもいいんだな」と、私は密かに鼻白んだ。ちょっと見損なった気分。憤慨もしていた。ひたすらあとをついていけばいいと思っていたケイミ先輩がいなくなることに、私はとても傷ついていたのだと、当時の私は気づけなかった。
いまならケイミ先輩の気持ちがよくわかる。当時の彼女は30代前半だったはずだ。どこまでも続くはずの道をがむしゃらに走っていたら、突如断崖絶壁が現れた時の絶望が。どんなに頑張っても、イキのいい若い女は特攻隊員としてしか有用しない会社では、これ以上の活躍は望めない。かといって、破天荒キャラのまま仕事を続けるのもキツいだろう。先を見越して積み上げていくような小賢しさは、ケイミ先輩にはなかった。そもそも、ケイミ先輩は筋の通った仕事をして、みんなでイエーイ!と喜ぶために働いていたのだ。
男連中はといえば、アウトローを気取りながら、誰にも悟られないほど微妙なグラデーションで、上手に権力志向へと色を変えていった。ケイミ先輩には、そんなことはできない。社内の政治になんて、興味の欠片もないだろうし。
子どもを持つことを考えたら、毎晩痛飲するような生活は続けられないとも思っただろう。しかし、痛飲しないとやっていられない仕事でもある。夢中になれるからこそ、中途半端な距離でそばにいたら、一本気なケイミ先輩の胸は苦しくなってしまう。ケイミ先輩には調整ツマミはついていない。オンかオフかの二択のみ。だから、去ると決めたのだと思う。この会社には、ケイミ先輩がありのままで働き続けられる居場所がなかったということ。でも、ケイミ先輩のありのままって?
いま思えば、気の強さだって、口の悪さだって、破天荒なエピソードだって、男ばかりが偉くなっていく会社で負けないための、ケイミ先輩なりの武装だったかもしれない。ありのままでもなんでもなかったとしたら? 悔し泣きのケイミ先輩を静かに見守るだけで、なぐさめの言葉さえかけられなかった自分が歯がゆい。
気付けば私は、ケイミ先輩よりうんと年上になっていた。いまさら「お疲れさまでした」と先輩の肩を抱き、ねぎらいの言葉をかけることはできない。若かった私は、なにも知らなかった。みんなでイエーイ!なんて、どうでもいいとも思っていた。言いたいことはわかるけど、そんなの子どもじみていると。しかし、いま改めて思う。みんなでイエーイ!と言えない仕事は、やっぱりつまらない。
ケイミ先輩はのちに子を産み、子育てがひと段落したところで働きに出た。どこにでも再就職できるキャリアがあったのに、同じ業界に戻ってくることは二度となかった。だけど、ケイミ先輩にとってなにが幸せかを私がジャッジするなんて、いちばん不遜なことなのだ。
のちにご尊父の葬儀でお会いしたとき、ケイミ先輩は私たちの顔を見るなり、「ねえ、このあとどこに飲みに行くの?」と尋ねてきた。相変わらずだなとホッとしながら、やっぱりもう少し一緒に働きたかったなと、ケイミ先輩が肩肘張らずに働き続けられる社会であって欲しかったなと、私は思った。