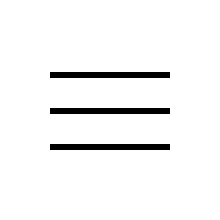「おつかれ、今日の私。」vol.6
東京生まれの日本人。
現在、TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」のMCを務める人気コラムニストで作詞家、プロデューサーのジェーン・スーが、毎日を過ごす女性たちに向けて書き下ろすエッセイです。
おつかれ、今日の私。 vol.6
否応なしに生活スタイルが変わり、一日3食自炊するようになった。期間限定だとわかっているからだとは思うけれど、それほど苦ではないのが我ながら驚きだ。
私は料理にほとんど興味がない。美味しいものは大好き。だけど、大きな体をしているわりに食に対する探求心が乏しい。味つけは塩と胡椒で十分だし、夫や子どもに食べさせなきゃいけないわけでもないから、レパートリーも増えない。自分以外に作ってくれる誰かがいるなら万々歳で、食器やカトラリーもこだわらない。使用頻度が最も高いのはローソンでシールを集めるともらえるミッフィーのボウル。自分のためだけならこれで十分だ。
スーパーでは決まって、肉、魚、野菜、豆腐や納豆などの豆製品、チーズなどの乳製品、卵、わかめやこんにゃくを買う。毎度毎度、それを煮たり焼いたり炒めたりして食べる。いまは糖質制限をしているので、主食はよほどのことがないと食べない。たいてい一皿料理だ。昔付き合っていた男に、「君は3品作れる材料を全部炒めて一皿にするね」と言われたことがあるけれど、あれは誉め言葉だったと思っている。
そんな簡単な作業でも、たまに面倒くさくなることがある。そういう時は、決まって料理上手だった母親の顔を思い出す。母は専業主婦だった。映画雑誌の編集者という花形の職業婦人だったが、結婚を機に家に入ったクチ。仕事を辞め私を産んで母親になった彼女を、私は家事をやる人だと思っていたフシがある。毎食毎食、作ってくれるのが当たり前だと思っていた。それが母親である女の役割であると、疑うこともなかった。
「飯炊きおばさんじゃないのよ」と母が文句を言うことがあった。本気で怒っているわけではなかったが、大事なことを言っている顔をしていた。私は茶化したり曖昧な返事をしたりして、それをやり過ごし続けた。どうやって答えたら、いや、応えたらいいのかわからなかったから。
母が、家族の誰かが作ったご飯を食べたことは一度もない。椅子に座ってでき上がりを待ったことも、「ごはんよー」と声を掛けられてから食卓に向かったこともない。私は食後の食器洗いを高校生時代くらいからやっていたと思うけれど、作って母に食べてもらったことはない。
家族という集団のなかで、労力を伴って繰り返し誰かになにかをしてあげる行為は、家事をメインに担当しがちな母親に集中する。我が家ではそうだった。外で稼いでくるのがメインの役割であるお父さんには良くも悪くも会社での評価がつくし、勉学が仕事である子どもには学校から成績がつく。だけど、お母さんの家事労働には? 食器洗い以外に手を動かさなかった昔の自分を思うと、母に対して申し訳ない気持ちでいっぱいになる。私は馬鹿じゃないのか、ほんとに。恥ずかしいよ。労って、代わってあげたってよかったのに。
母だって、ひとり気楽に暮らしていたら、献立に頭を悩ませることもなかっただろう。朝ごはんが終わったそばから「お昼はなに?」と聞かれることもなかった。いまの私のように好きなものを適当に作って、好きな時に食べていたと思う。母は「作る時間は結構かかるのに、食べるのはあっという間ね」と苦笑いをすることもよくあった。私はと言えば、ただただ「美味しい!美味しい!」と食べていただけ。皿ごとに丁寧な感想を伝えることなどなかった。母はとても料理が上手だったというのに、率先して習うこともなかった。母が作る青椒肉絲とビーフストロガノフは絶品だったのに。
豚コマとレタスに塩胡椒し、オリーブオイルで炒めただけのワンプレート昼ご飯をスマホ片手に食べながら、もう取り返しが付かないのだと私は肩を落とす。母は私が24歳の時に没してしまったから。
母が没したあと、しばらく父に朝食を作っていたが、新聞を読みながら食べ、文句だけはちゃんと言うのにウンザリだった。でも、生前の母に対する私の態度に大差はなかったとも思う。あの頃に戻ることができるのなら、週に2回は夕飯を私が作ろう。弁当も自分で作り、たまには母の分まで作ってお昼に食べてもらおう。お父さんに頼んで、食器洗い乾燥機をプレゼントしよう。買い物には一緒に行って、重い荷物を持ってあげよう。ああ、全部生きているときにやってあげられればよかったのに。本当にごめんなさい。
食べた皿と箸とフライパンをちゃっちゃと洗い、もう一度母を思う。大人になった私が風邪ひとつひかないのは、あなたがきちんと私を食べさせて、丈夫な体を作ってくれたからに違いない。母親業、本当にお疲れさまでした。いまはひとり、天国で好きなものを作って食べているだろうか。