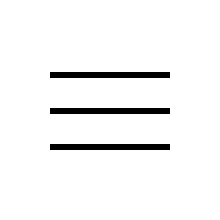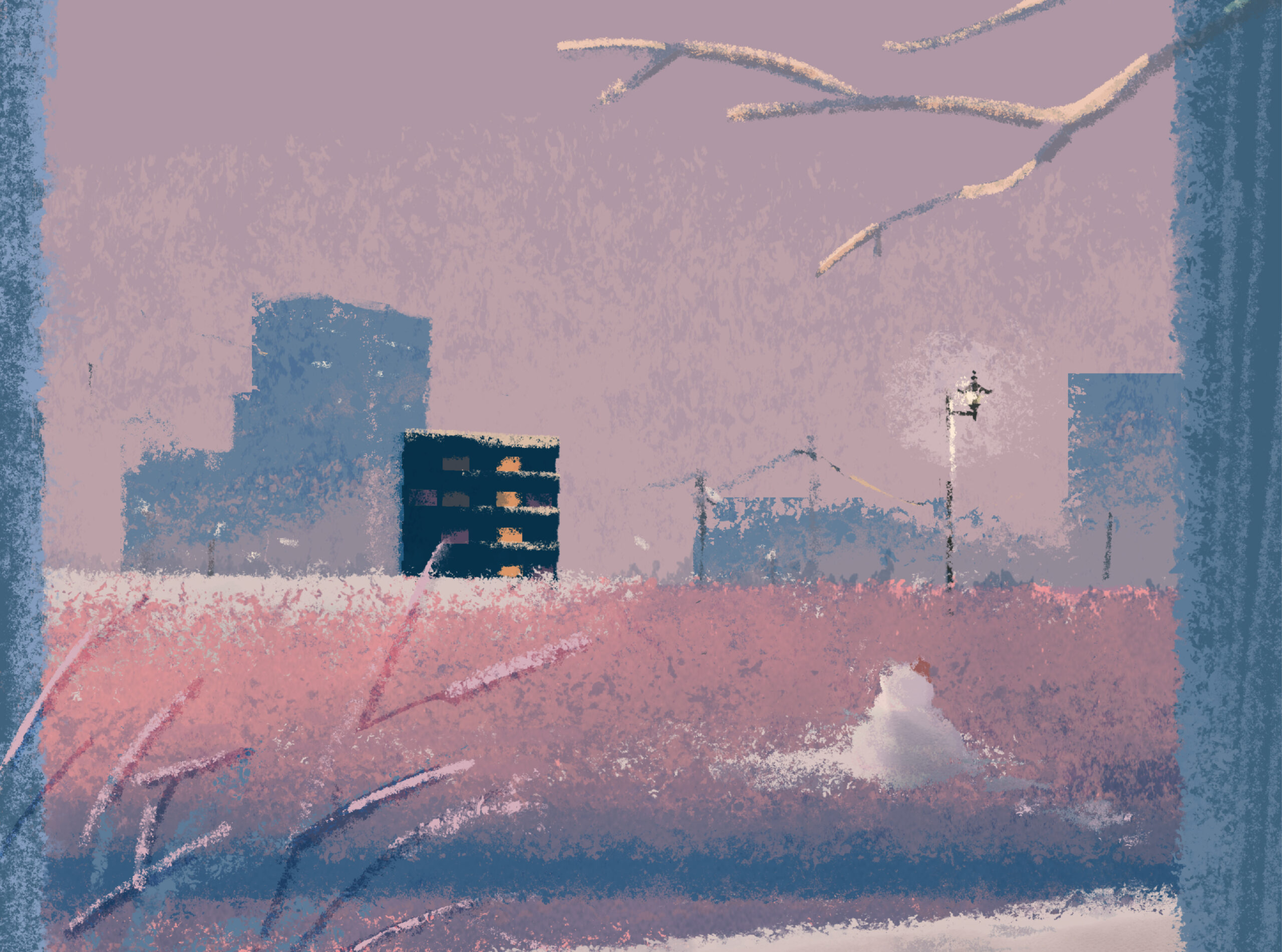「雨の夜にだけ会いましょう」
「定期的に集まろうぜ」と言い出した飲み会は二回目が開催されない。
仕事も遊びの約束も、数週間先の予定を詰められるとなんだか心が重くなる。
「もっと雑で、ちょうどいいこと」を求めて、無責任な願望を言葉にしてみるカツセマサヒコの妄想コラム連載です。
第十三夜 あちらのお客様から五億円です
かれこれ12回もやってきた連載なので、そろそろ読者の方もお気付きと思いますが、私はとてもビビリで、小心者なのです。
たとえばこうしてコラムを書いていて、記事が公開されたあと、自分のSNSで恐る恐る告知投稿をします。すると、引用RTされたことだけはわかるのに内容は読めない時があり、もしかしてこれは、どこぞの鍵アカウントが私には見えないところでボロクソに記事の陰口を叩いているのでは? と、ネガティブな方向で可能性を探ってしまうのです。
こういうとき、一度でも悪いほうに勘繰ってしまうと、もう頭からネガティブが抜け出ることはありません。狼狽した私は思わずスマートフォンをクッションに放り投げ、「つらー!」と叫び、そのあと、投げてしまったスマートフォンが壊れてないかやさしく撫でながら念入りに確認するのです。
そんな大橋以上にちっぽけな心臓を持つ私なので、チェーン店ではない個人経営の飲食店に入るのにも、ものすごく勇気が要ります。たとえば個人経営の喫茶店の前に立てば、もしも店主が気難しそうな人だったらどうしよう。メニューの見方がわからなかったらどうしよう。そもそもメニューがない店だったらどうしよう。「趣深い」とかのレベルじゃ済まない汚さだったらどうしよう。全然美味しくなかったらどうしよう。常連客ばっかりだったらどうしよう。謎な絡まれ方したらどうしよう。などと、不安が次から次へと湧き出てくるのです。
だから、妄想の世界でくらい、小洒落たバーの常連客になりたい。
そのバーはバーテンダーでもあるマスターが、なんかよくわからない会社を経営する傍ら、副業で始めた小さな店です。いつも信じられないほど照明が暗く、駅からも遠いこともあり、7名掛けのカウンター席は金曜の夜でもフルで埋まることはほとんどありません。
「全然赤字ですけどね」とにこやかに語る白髪のマスターの目は確かに死んでいますが、ほかに雇っている従業員もおらず、酒を作るのは遅いが傾聴のプロであるマスターに少しでも自分の話を聞いてもらおうと、今夜もたくさん(といっても7名掛けの席が埋まることはないくらいの人数)の売れない芸人みたいな人たちが、さまざまなエピソードを引っ提げてこの店に集まってくるのです。
「いや実はねマスター、このまえ、アパートの隣の部屋に住んでるお姉さんが超大量の梅水晶を作ってうちにやってきたんですけど」「聞いてくださいよマスター、このまえ四度目の初詣に行っておみくじを引いたら好きな子と二人して大凶だったんです」「マスター、深夜の公園って女に呼び出されるためにあると思いません?」
数々のしょうもなさすぎるエピソードを小耳に挟みながら、自分はというと、家から持ってきた文庫本を黙ってじっくりと読んでいるだけなのです。マスターは、本を読んでいる人がいると、そちらに小さなライトを無言で向けてくれます。そんな気配りができる人です。ジンリッキーを2杯ほど飲みながら、いつものように文庫本を読み、たまに常連客から「ねえ、今のおもしろくなかった?」とか雑な絡みをされて「ハハっ」と鼻で返すような、そんな夜を週に1~2回過ごせたら、なんとも最高にパーフェクトデイズな香りがしませんか。
その日も、仕事で疲れ果てた状態で、なんとか最寄り駅まで帰ってこられました。体力的には限界ですが、しかし、このまま家に帰って風呂に入って眠るだけでは、疲れは取れないというかなんだか気力が回復しない。どうしたものかと悩みながら商店街を歩いていると、ちょうど駅と自宅の中間地点あたりに、いつもバーがあるのです。
「今日は、誰もいませんように」
疲れ果てて誰とも喋りたくない私は、マスターと話すのすら億劫だと思いながら、しかしこの店の酒はとびきり美味いのです。明日働くぶんくらいの気力は回復してくれそうだと、僕はバーの扉を開けました。カランカランとドアのベルが鳴った後、店内にはどこかで聴いたことのあるジャズが小さなボリュームで流れていて、さらに幸いなことに、暗い店内にはマスター以外誰もいないように見えました。これなら落ち着いて酒が飲めるし、かばんに忍ばせておいた文庫も集中して読むことができそうです。
「じゃあ、マスター、いつものやつを」
ここで「いつものやつ」と言えるのが、バーの常連ならでは。マスターに必死に覚えさせた甲斐あって、僕の手元にはジンリッキー(薄め)がすぐに出てきました。唇を湿らす程度にそれを口に含むと、やれやれ、村上春樹の初期作品の文庫本を僕は静かに読み始めました。
しかし、ここでマスターが、なにやら不自然な動きを見せはじめたのです。目の前にいたはずのマスターは突然しゃがみ込むと、カウンターの下から人間が2人は入りそうな超巨大スーツケースを取り出し、乗るはずもないカウンターテーブルにどかんと音を立てて乗せ、そのまま左右15桁ずつのナンバー式ロックを解除したのです。
「あちらのお客様からです」
そう言いながらマスターがスーツケースを開けると、中には5億円が入っていました。そんなことあるかよ。
「ちょ、え、何ですかこれ?」
「あちらの、お客様からです」
マスターが何かを忠告するように再度そう言うと、右手を店の奥に向けました。そこには、僕のまったく知らないおっさんが座っていました。
「え、だれ?」
お金のことよりもまず、その不審なオーラが気になり、僕はいつでもスーツケースを投げつける準備をしながら、彼の反応を待ちました。5億をくれようとしているおっさんは、今にも5億をくれようとしている雰囲気を漂わせたまま、言いました。
「俺です。あなたのコラムを、鍵アカウントで引用RTしてたやつです」
こっわ。実在するのも怖いし、同じ店にいるのかよ。
「僕は世界で13番目の金持ちでして。まあ、知らないですよね。13番目に高い山も13番目に長い川も知られていないように、13番目の金持ちも誰も知らないでしょう。でも、金はあるのです。油田もあるのです。で、あなたのコラムが本当におもしろい。なので、まあ慈善事業と言いますか。とりあえず5億ね。非課税でいいですから。振り込んでおきますよ、そちらを」
まっっっったく人生は楽勝だぜ。
僕は「まじでか」と2千回くらいつぶやいてから、13番目の金持ちに何度もお礼を言って、無事に5億円をゲットしたのでした。
このくらい。このくらい雑でちょうどいい出来事が、来世あたりで起こりますように。