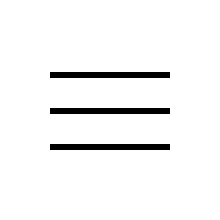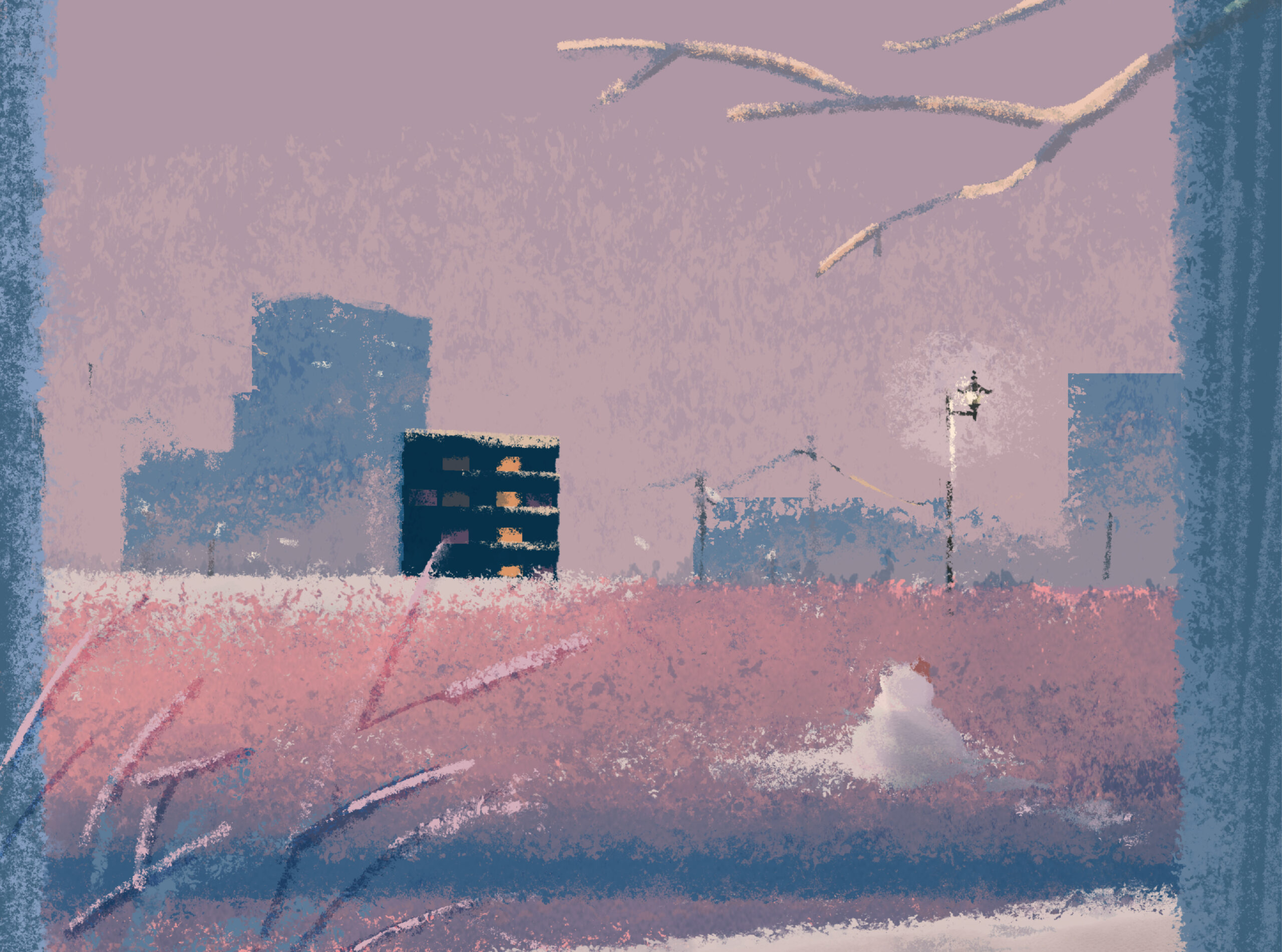「雨の夜にだけ会いましょう」
「定期的に集まろうぜ」と言い出した飲み会は二回目が開催されない。
仕事も遊びの約束も、数週間先の予定を詰められるとなんだか心が重くなる。
「もっと雑で、ちょうどいいこと」を求めて、無責任な願望を言葉にしてみるカツセマサヒコの妄想コラム連載です。
第八夜 深夜の公園は呼び出されるためにある
今年の目標を決められないまま、一年が終わろうとしています。
気付かぬうちに流れゆく時間。その感覚は年々早くなって、この調子でいけばアッという間にじいちゃんになってしまいそうです。虚無虚無プリン。
そうなる前に、もう少し人生を充実させねば! などと思ってはみるものの、歳を取れば取るほど、荷物は増え、足取りは重くなっていく。昔は無限の可能性があったかもしれないが、今は自分のできる範囲のことをずる賢くこなしていくだけで精一杯。なんか無茶しようとか、そういう気力が起きにくい。大人ってこういうことなのね〜、などと思いながら、せめて頭の中でくらい、楽しい妄想を繰り広げていたいと筆を走らせてみるのです。
深夜の公園って、良くないですか?
ドリカムの名曲『サンキュ.』の歌詞に、“彼と別れたことを友人に連絡したら公園まで駆けつけてくれて、横で笑い話したり鼻歌うたったりしてくれた”というシーンが出てくるのですが、「これは男友達だったら確実にワンチャン狙っているだろう」とSNSに投稿したところ、にわかに炎上しかけたことがあります。
「男女の友情」とか「男女の関係」とかそういう言葉ってこの時代に馬鹿馬鹿しいよね〜。男と女がいればすぐに恋愛だとかそういうふうに捉え出すの、まじで古いよね〜。
価値観のOSアップデートに失敗しまくる人生。それでもこの妄想連載は止まることができないのです。ワンチャン狙うつもりはなくとも、深夜の公園に、古くからの女友達から呼び出されてしまうのです。
「本当に来るとは思わなかった」
石造りの大きなタコさん滑り台の上に小さくしゃがみこんでいたその幼馴染みは、呆れるように言いました。
「呼んでおいて、その言い方はないだろ?」
本当は、呼ばれてたまらなく嬉しかったのに、それを表情には微塵も出さないように気をつけながら、僕は声を低くして言いました。
「なんかあった?」
タコさん滑り台の梯子をカンカンと登って、彼女のそばに近づくと、持っていたホットのペットボトルを彼女に渡しました。彼女は小さくありがと、と言ってそれを受け取り、ボトルのラベルを見つめました。
「別に、大したことじゃないんだけどさ」
拗ねたように口を尖らせる幼馴染み。可愛い〜〜〜! と悶えそうになるのを堪えながら、僕もその横に腰掛けます。静かな公園。住宅の灯りはほとんど消えていて、街の寝息が聞こえてきそうです。
「大したこともないのにわざわざ呼ばないでくれよ」
「どうせ暇だったでしょ?」
「忙しいんだよこっちも」
本当は家で五時間近くゼルダの伝説をやっていただけなんですけど。五時間くらいゼルダの伝説をやると、街の外にあるものも大体は「ゼルダにありそう」と思えてくるから不思議です。
「で、どしたの。また彼氏と別れた?」
そう、この幼馴染みは、恋多き人なのです。ひっきりなしに彼氏を作ってはなかなか長続きせずに別れる、ということを繰り返しているのです。幼馴染みとして、まあ心配なのです。
「まだ別れてないし」
「まだ、ってなんだよ。喧嘩したとか?」
黙って頷く、幼馴染み。
そんなことで家を飛び出すんじゃないよ。しかもわざわざ、ほかの男を深夜の公園にまで呼び出すんじゃないよ。
「彼が追っかけてきたらどうするわけ? 公園とはいえ、男と会ってたとか、ダメじゃね?」
「あー絶対に追いかけてきたりしないから。そういうタイプじゃないから」
「そなの?」
むしろそれは、付き合ってていいのか? 疑問符が頭をよぎりますが、何も言わずに見守るしかありません。幼馴染みとはそういうものです。
「単純に、大事にされてないの。家政婦みたいに思われてるだけ」
「それはお前、よくないやつだろ」
「そうだよ、よくないよ」
そんなのわかってるよ、というニュアンスが込められまくった言い方に、思わずこっちもムッとします。ムッ。
「料理作っても不味いとか言われるし、服とか全部脱ぎっぱなしで、片付けろっていうと何故か私が怒られるし、お酒切らしてても怒鳴られるし、前戯ないし」
「何それ、最悪じゃん」
「うん」
「同棲してんのに家政婦みたいってな、それ、お前のこと、彼女として尊重してないってことだぞ? そんなんでいいのかよ? なあ、もっといい男いるって、本当に」
「あー言わないで、言わないで!」
彼女は両手をバタバタと振ってから、その手で自分の耳を塞ぎました。
「私の彼氏に文句言っていいのは私だけだから。あんたが彼氏の悪口言うの、やめて?」
何それ、むっずーーー。むっずーーーーーーーーーーー。
じゃあ何のために呼ばれたんだよ、とペットボトルのキャップを開けながら愚痴ると、「ただ黙って、横に座ってて欲しいだけ。気が済んだら帰るから。ごめんね」と、彼女は言うじゃありませんか。
そんな不幸な恋、俺が全部、奪い去ってやるよ。
イケボで言いたい。今なら言える気がする。てか、今しかそのシチュエーションはない。急に勇気を奮い立たせようとしますが、なかなかエンジンは温まりません。くそ。やっと俺のチャンスが来たと思ったのに! と、歯痒く思っていた矢先、彼女が携帯電話を取り出して、「あ」と小さく声を出しました。
「どしたの」
画面を覗き込むと、例の彼氏と思われる男からのLINEが一通、届いています。
「“ごめん”だって。謝られたの、初めてかも……」
「え? なんでそれだけで嬉しそうな顔しちゃってんの?」」
恋って、つえーーー。悪い男って、すげーーーー。
僕はすっかり恋の沼に落ち切ってしまっている幼馴染みの横顔を見つめながら、「まあ、いいよ。なんかあったら呼んで。いつでも行けるようにしとくから」と、できるだけ余裕のある男を演じて言うのでした。
「ん、サンキュ」
その言葉を聞いた途端、ドリカムの歌詞の意味がようやく少し理解できましたとさ。
このくらい。このくらい雑で、ちょうどいい出来事が、来世あたりで起こりますように。
第九夜へ続く