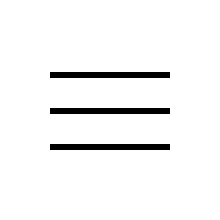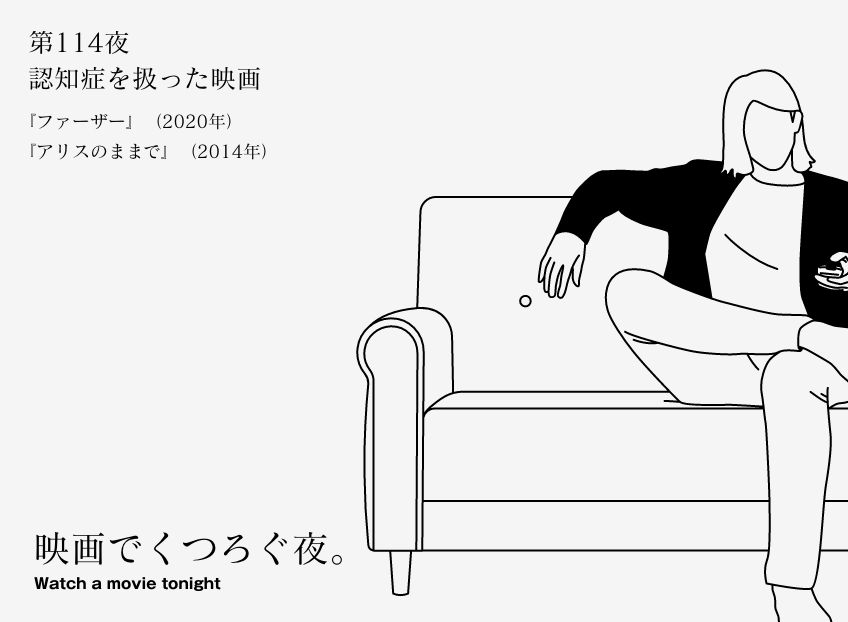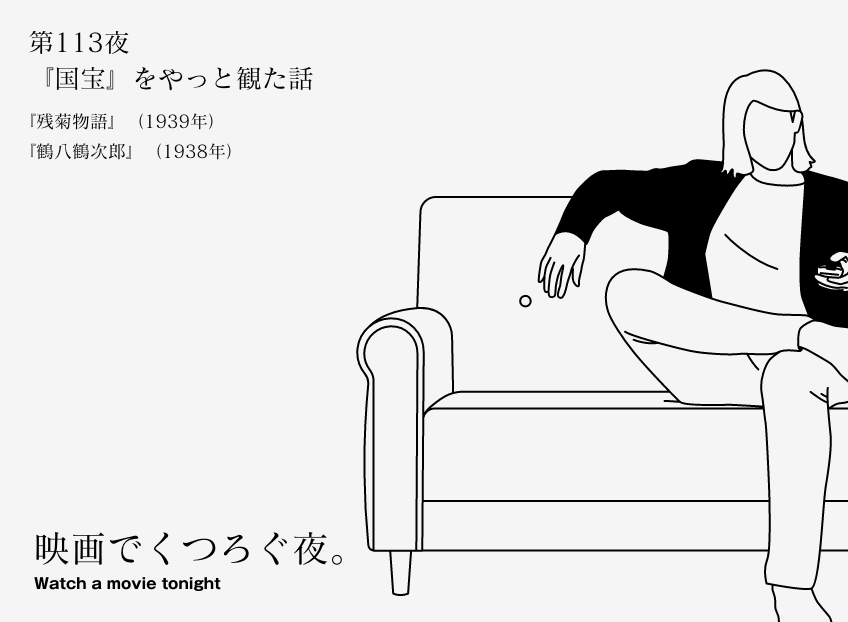真魚八重子「映画でくつろぐ夜。」 第10夜
Netflixにアマプラ、WOWOWに金ロー、YouTube。
映画を見ながら過ごす夜に憧れるけど、選択肢が多すぎて選んでいるだけで疲れちゃう。
そんなあなたにお届けする予告編だけでグッと来る映画。ぐっと来たら週末に本編を楽しむもよし、見ないままシェアするもよし。
そんな襟を正さなくても満足できる映画ライフを「キネマ旬報」や「映画秘宝」のライター真魚八重子が提案します。
■■本日の作品■■
『ピクニックatハンギング・ロック』(75年)
『blue』(01年)
※配信サービスに付随する視聴料・契約が必要となる場合があります。
女子校と映画
愛知県の田舎町出身なので、ミニシアターのような独特な劇場は近所にはない。小学校時代から色々な映画が観たかったわたしは、映画館に行きたい一心で、受験をして中学から私立の女子校に入った。当時は名古屋を走る地下鉄の東山線沿線に、ミニシアターは集中していた。なので東山線を利用する私立に入学した。12歳にしては随分思い切ったわがままを言ったものだし、親もよく許してくれたと思う。
中高一貫校だったので、そのまま高3まで女子の中で過ごした。大半の子はそのまま大学までエスカレーター式に推薦入学で進学したが、わたしは6年通って飽きてしまっていたので、別の大学に受験で入った。宗教学科という変わった専攻をしたせいか、いきなり男子110人に対して女子19人だけという、男子校に迷い込んだような極端な環境になってしまった。また、それについては改めて書くとして、中高を女子校に通った感想としては、結局自分的には良かったと思う。
女子しかいない環境は快適だった。男子の目がない状態でガサツだったかもしれないけれど、取り繕う面倒がなかったのは、もしかしたら率直に物を書くことに慣れる素地になっているかもしれない。今でもどこか、女性だったら書くべきではない部分をわかっていなくて、気づかずに書いてしまっている気がする。
マンモス校だったので、色々な子がいた。一応お嬢様学校で不良はいなかったけれど、段々実際はそうでもないことはわかってくる。名古屋の私立学校は校則が厳しく、異性交遊禁止だったので、男子と歩いているところを見つかっただけで補導される。そのせいか、自然とみんな口が堅かったのだと思う。お互いに秘密を握っていて「バラしたらバラされる」といった一蓮托生の友人関係で話すくらいで、先生の耳に入るような迂闊な噂話はしなかった。
稀にわたしも、そういったこっそりする会話に参加したことがあった。学級委員をしていて真面目だと思っていた子や、国体を目指しているような運動部の頑張り屋が、じつは夜遊びをしていると話していて、イメージとの違いにビックリした。共学だったら学校内でカレシを見つけることが多そうだが、女子校の生徒は基本的に外部の人間と交際することになるので、学校以外に別の世界を持っている。年齢も同世代が相手とは限らない。だから、秘密のある子はさらに大人びて見えていた気がする。
でも、本当に純粋でウブな子が「わたしは高校入ってから、お父さんと駅員と先生以外の男の人と、口きいてないよ」と不意に言い出して、つい笑ってしまったけれど、普通に暮らしていたらそういうものだろうなと思ってもいた。
自分の放課後の世界がある子たちは、そちらが本当の姿だ。学校にいる十代風のほうが嘘をついている。学校は卒業という肩書のために必要な場所と時間で、当たりさわりなく過ごしたほうがいい。だから学校での真面目な様子は、先生からヘンな注目をされないように、おとなしくやりすごすかりそめの姿なのだ。今の十代の子はもっと開放的に過ごしているのだろうか? 今思えば、わたしたちが自由であるために身に着けたごまかしの方が、より不健全だった気がする。
『ピクニックatハンギング・ロック』(75年)
『ピクニックatハンギング・ロック』
監督:ピーター・ウィアー
原作者:ジェーン・リンジー
出演者:レイチェル・ロバーツ/アン・ランバート/ドミニク・ガード
世界一美しい女子寮映画。ピーター・ウィアーはオーストラリアの名匠で、アメリカに渡ってからも良作を手掛ける監督。名門女子学園の生徒たちが、ある日岩山へとピクニックに行く。白いゆったりとしたワンピースが非常に魅力的で、お互いにコルセットを絞める身支度の姿もしなやかで可憐だ。
少女たちは草原でゆったりと過ごすが、昼が近づくとともに、幻惑に襲われたように夢うつつとなっていく。そして強い誘惑に抗いがたく、岩山へと自然に足を進め岩間に消えていく。彼女たちはそのまま神隠しのように消息を絶ってしまう。オーストラリアの日差しと冷たい岩肌。少女たちの儚げな存在感。大人になって神秘性を失ってしまうよりも、十代の美しいうちに消えることを選ばれたような、超自然性を感じる物語である。不可思議で謎めき、恐ろしげな雰囲気もたたえた少女映画の究極形。
『blue』(01年)
『blue』
監督:安藤尋
原作者:魚喃キリコ
音楽:大友良英
出演者:市川実日子/小西真奈美/今宿麻美/仲村綾乃/高岡蒼佑/村上淳
もう20年も前の映画だというのが驚き。十代の女子の透明感の写し取り方がハンパない作品だ。市川実日子の演じる美大への進学を考える女子高生は、まったく古びないどころか、今見ても個性的で存在感自体がおしゃれだと思う。
桐島(市川実日子)はいつも一人でいる大人びた遠藤(小西真奈美)が、なんとなく気になっている。遠藤はなんらかの事情で昨年停学処分になっており、一年留年している謎めいたクラスメイトだ。桐島は遠藤を昼食に誘い、二人は次第に仲良くなっていく。
ありがちな合コンやありがちな初体験よりも、大事な友人とただ海辺へ出かけた時間が美しい記憶となることを、映画は表す。ただ、決して一番の友人が疑似恋人になる必要はない、という違和感だけは、初見の時から感じてはいるけれど。こういう十代の一日が過ごしたかったし、過ごした人は羨ましいと思う。
※配信サービスに付随する視聴料・契約が必要となる場合があります。